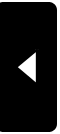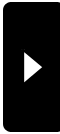2017年06月30日
伊那街道(飯島宿~清泰寺(松川町))
2 コース 飯島陣屋ー慈福院(飯島町)-清泰寺(松川町)
3 所要時間 5時間(昼食、見学含む) 約10キロ
(クリックして大きくして見てください)
守屋貞治作・延命地蔵菩薩
徳本上人名号塔
徳本上人名号
江戸時代に幕府が直接支配した領地(天領)に置かれた役所の飯島陣屋を見学しました。信濃の国の天領は、南信の飯島、東信の御影(小諸市)、北信南部の中之条(坂城町)、北信北部の中野(中野市)の4カ所の陣屋が中核を担いました。飯島宿は約1キロに及んでいたとのことですが面影はありませんでした。
飯島町慈福院には高遠の石工・守屋貞治作の延命地蔵菩薩が、松川町の清泰寺には徳本上人名号塔、徳本大行者座像がありました。今年は徳本上人の200回忌にあたります。 参加者 23名
徳本上人について
江戸時代にとびぬけて優れた念仏僧で、生涯を修行と念仏布教活動に身を捧げ、皇族、将軍家、諸大名、一般民衆まで多くの人から信仰された。徳本上人が書かれた名号文字は速書きで、丸みをおびた特徴がある。お説教は法然上人の一枚起請文にある「ただ往生極楽の為には南無阿弥陀仏と申して疑いなく」日々お念仏を唱えることの重要性を説いた。木魚と鉦を激しく乱打して皆でお念仏を称える独特の念仏。
2017年06月30日
伊那街道(宮田宿~飯島宿)
2 コース 宮田駅ー赤須上穂宿ー安楽寺ー聖徳寺ー飯島宿
3 所要時間 5時間(昼食、見学含む) 約10キロ
(クリックして大きくして見てください)
高遠領界碑
安楽寺如意輪観世音
不動明王(小町屋光前寺道標)
大型名号塔(六斗名号塔)
街道は田切地形の河岸段丘上にあり、洪水時には川が氾濫し橋が流され渡河に大変苦労したとのことです。大田切川は天保3年(1832)に1年間で8回流された記録があり伊那街道有数の難所でした。
駒ケ根市の赤須上穂宿(赤須村と上穂村の境に伊那街道が整備され15日ごとに交替で伝馬荷の継送りを担った合宿)の中心部にある安楽寺と駒ケ根市の如来寺、飯島町の聖徳寺には今までに見たことのない大型名号塔がありました。深堀された名号塔は、一字に米が一斗入る六斗名号塔(南無阿弥陀仏)で見事です。安楽寺には高遠の石工・守屋貞治36歳初期作の文字碑庚申塔と個性的な如意輪観世音と墓地には井筒屋の地蔵尊があり一見に値します。山門前には徳本上人信濃巡錫時の名号塔があります。 参加者 23名
2017年06月02日
権兵衛街道(萱ヶ平~権兵衛峠~北澤合流点)
2 コース 木曽町日義萱ヶ平ー権兵衛峠ー合の沢観音ー鍬入岩ー
茶屋跡ー七曲ー北澤合流・遊歩道入り口
3 歩行時間 3時間30分 約8㎞
4 主 催 NPO法人 木曽川・水の始発駅 参加者20名
(クリックして大きくして見てください)
権兵衛街道は、伊那と木曽を結ぶ権兵衛峠を結ぶ街道で、木曽日義村神谷の牛方・古畑権兵衛が、木曽11宿に呼びかけ、伊那側15か村の協力を得て牛が通れる道を完成させました。以後、伊那からは大量の米が、木曽からは漆器などが牛によって運ばれました。
出発地の萱ヶ平は奈良井川に沿って南に入る谷(川入)の一番奥の集落で現在も2軒が居住しています。かつては番所が置かれ賑わっていましたが、現在は数件の家屋が確認できる程度の寂しい集落でした。街道の木曽側は道もしっかりしており歩くのに問題はありませんが、伊那側は傾斜もきつく一人が通れる登山道といった状況です。明治44年(1911年)に国鉄中央線の全通により、往時の賑わいは失ったものの、昭和30年頃までは行き交う人がいたとのこと。峠は権兵衛の碑や歌碑があり、木曽駒ケ岳の登山口になっています。
峠から少し入った所に伊那用水路跡(木曽山用水)がありました。いつの世も水は人間が生きるための生命線であり、かんがい用水に苦しむ伊那西部上部集落のために木曽谷から引水した歴史跡が残っていました。実現には水利権の問題があり相当苦労したとのこと。先人の知恵と苦労と努力に驚きました。
2017年05月30日
秋葉街道てくてく旅信州編(伊那市長谷溝口~高遠城址)
2 コース 溝口ー非持ー高遠城址
3 所要時間 3時間 約8㎞
(クリックして大きくして見てください)
(高遠の名匠石仏師・守屋貞治の傑作)
溝口から高遠城址に向かって三峰川を下ると間もなく非持になります。地名に関心と興味がありましたが、「検校塚」で鷹匠・依田豊平が一条天皇の鷹を見事調教したとして非持を荘園として賜ったことが判りました。中非持の三峰川と山室川の合流地点には、大明神石仏群があり駒ケ岳の登山口としてかつては鳥居が建ち遥拝所があった山岳信仰ゆかりの地でした。今回のてくてく旅で最も印象に残ったのは、伊那市高遠原勝間の常盤橋たもとにあった大聖不動明王でした。高遠の希代の名匠石仏師・守屋貞治の最高傑作です。高遠の石工は全国で活躍しており、守屋貞治は円空に匹敵する石仏師だと思います。上諏訪の諏訪家菩提寺「温泉寺」にも多くの石仏が残っています。
2017年05月30日
善光寺街道(会田宿~西条宿)
2 コース 四賀支所ー会田宿―立峠ー乱橋宿ー中ノ峠ー西条
3 所要時間 3時間30分 約8㎞
(クリックして大きくして見てください)
松本平から善光寺平へ出るには、刈谷原峠、立峠、猿ヶ馬場峠の三つの峠を越えます。今回は最大の難所と言われた立峠に行きました。会田宿からほどなく岩井堂の磨崖仏に立ち寄りましたが、信州には珍しく11体あるとのことです。立峠の峠口には見たことのない石仏「三面六臂馬頭観音像」が鎮座し街道を見守っていました。恩愛の心が伝わる美しい像で善光寺街道随一の大きさとのことです。峠まではわずか600㍍の距離ですが、いきなりの急坂のためけっこう汗をかきました。峠には茶屋が三軒あったとのことです。峠から乱橋宿までは車が1台通れる道があり800メートル続いた石畳もありました。宿場は中町、本町は名ばかりで店はまったくなく過疎化が進んでいます。中ノ峠を越えて西条まではわずかに往時の面影を留める程度で、地域一帯の農村風景が心を和ませてくれました。
2017年05月08日
秋葉街道てくてく旅信州編(伊那市長谷中尾~市野瀬宿)
2 コース 戸台口ー中尾ー市野瀬宿
3 所要時間 2時間 約4㎞
(クリックして大きくして見てください)
戸台口から中尾橋を渡り間もなくすると中尾集落になります。江戸時代から伝わる中尾歌舞伎が昨年、後継者不足で中止になり残念に思っていましたが、中尾座の建物だけでもと念願が叶い嬉しかったです。伝統文化が途切れた悔しさはありましたが、立派な建物は残っており是非とも早期再開をしてほしいと思いました。街道筋には中尾の辻に極小の双体道祖神が、郷坂には白衣観音が、道中には秋葉街道の面影が色濃く残る杉林・雑木林が連続し、長谷集落の末端には宿場「市野瀬宿」が面影を残していて街道気分を味わうことができました。誰にも会いませんでしたが、落ち葉を踏んだ跡はあり古道めぐりをする人はいるなと思いました。
2017年05月05日
秋葉街道てくてく旅信州編(伊那市長谷粟沢~分杭峠)
2 コース 粟沢駐車場ー大曲ー六角小屋ー分杭峠
3 所要時間 往復 3時間 約10㎞
(秋葉街道 粟沢~分杭峠 上り1時間45分 約5㎞)
(クリックして大きくして見てください)
(撮影日4月14日予備調査時、雪が残ってます)
秋葉街道は静岡県浜松市にある火防(ひぶせ)開運の火の神を祀る秋葉神社を詣でる街道です。高遠からの最初の峠「分杭峠」は伊那市長谷と下伊那郡大鹿村の堺にありますが、最近は中央構造線上のゼロ磁場が有名になり、県外から大勢の皆さんが気を体験に来ています。シャトルバスで往復する方法が普通で秋葉古道にあまり関心はなさそうです。
シャトルバス粟沢駐車場から大曲まではアスファルト舗装、大曲から分杭峠は粟沢川沿いや急な山道を歩きます。街道の雰囲気が随所に残っていて面影を感じながら歩くことができました。ただし、参考本、パンフレットによっては中間点から峠間は通り抜けできないと表示されています。失敗しないよう事前に伊那市役所長谷支所に確認し事前調査をして当日に供えました。結果は途中からはピンク色のテープが随所に取り付けられており迷うことはありませんでしたが、連休中にもかかわらず地元の水管理のおじさん一人に会っただけで寂しかったです。
2017年05月05日
秋葉街道てくてく旅信州編(伊那市長谷溝口~戸台口)
2 コース 伊那市長谷地区を周回
溝口常夜燈、道標ー熱田神社ー八人塚ー戸台口ー
国道152号美和湖ー溝口六地蔵ー中央構造線溝口露頭
3 所要時間 周回時間 2時間30分 約6㎞
(秋葉街道 溝口~戸台口 上り約3㎞)
(クリックして大きくして見てください)
竜の彫刻と宝の玉(左) 六体道祖神
高遠から国道152号線を南に約7キロ行ったところに伊那市長谷(旧長谷村)の中心地溝口があります。この溝口には秋葉街道の常夜燈や自然石に掘られた「右 むら 左 あきは道」の道標、さらには、秋葉神社のお札を入れる箱柱や分去れには珍しい六体道祖神があり、秋葉街道の面影が感じられました。また、村の規模には不似合いの、伊那日光と呼ばれる国の重要文化財、熱田神社があり、力みなぎる竜や獅子の彫刻は見事で宝の玉を持った竜がパワースポットになっています。
溝口には日本最大級の断層である中央構造線が直接見れる露頭があり断層活動を垣間見ることができました。ここもパワースポットです。
2017年04月05日
中山道(馬籠峠~妻籠宿)
2 コース 馬籠峠ー一石栃立場茶屋ー大妻籠ー妻籠宿
3 所要時間 2時間 距離 5.5㎞ (妻籠散策 別に1時間 )
(クリックして大きくして見てください)
全国的な晴れに誘われて早春のウォーキングを満喫しました。平日のためか日本人には会いませんでしたが、外国人50人ほどに会いました。欧米人に人気があります。妻籠宿の散策では、団体バスで来られた観光客が大勢いましたが、欧米人と日本人の楽しみ方の違いを感じた一日でした。
2016年11月18日
野麦街道(松本~新村)
2 コース 松本牛つなぎ石ー荒井ー堀米ー下新ー新村駅
3 所要時間 約3時間 約9㎞
(クリックして大きくして見てください)
「右まつもと、左ひだ」
野麦街道の起点は、松本市本町と伊勢町の交差点です。ここに新設の道標「左野麦街道」と街道の面影を残す牛つなぎ石があります。ここから先は今年実施された松本歴史の里企画展の資料を参考に歩きました。島立地区はすでに市街化が相当進んでおり旧道がどこにあるのか見誤ることが多々ありました。奈良井川を渡った西側には荒井観音堂が、さらに先の堀米には「右まつもと、左ひだ」の道標がありました。高札場標識も二カ所あり、少ない目印等を頼りになんとか旧道を探しました。堀米地区は北アルプスが遠望でき切妻民家も沢山残っていました。旅人は北アルプスに別れを告げ、飛騨への旅路を急いだことと思います。起点から新村駅まで約9キロを歩きましたが、島立地区は田舎風情が残っていて安らぎがありました。
2016年11月13日
野麦街道(新村~新島々)
2 コース 新村ー三溝ー森口ー淵東ー新島々
3 所要時間 3時間 約8㎞
(クリックして大きくして見てください)
「左ハ大つま 右ハまつもと」
国道158号から離れた松本市新村地籍に野麦街道の案内看板がありました。一部ではありますが砂利道が残っていて懐かしかったです。この先の新村根石に「左ハ大つま、右ハまつもと」と記された道標があります。左(北)が梓川を渡り松本市梓川大妻へ行く道で、右(東)が松本へ行く野麦街道の分岐です。松本市波田三溝の安養寺はシダレザクラで有名ですが、この西側通りは旧街道の面影が残っていました。旧波田町の森口から淵東は、かつては松林が続いていたとのことです。その面影は波田小学校にありました。
松本電鉄上高地線終点の新島々まで約8キロを歩きましたが、野麦街道の面影が残る遺物や標識はごくわずかでした。限られた財産であり地域の皆さんのお力で是非残してほしいと思いました。
2016年11月05日
野麦街道(水没記念碑~田ノ萱~古宿~黒川渡)
2 コース 水没記念碑ー田ノ萱ー古宿ー黒川渡
3 所要時間 1時間30分 約5㎞
(クリックして大きくして見てください)
入山宿から次の集落、田ノ萱で古老に野麦街道を訊ねましたら「水没記念碑から田ノ萱間はダムの湛水底や藪になっているところが多い」との事でした。仕方なく新道を歩くことにしましたが、標識がところどころにあり旧道との交わりは雰囲気でわかりました。田ノ萱からは祠峠が良く見えました。祠峠は以前「奈川自然案内人の会」の主催で訪れたことがありましたが、この峠は旧奈川村と旧安曇村大野川(乗鞍へ行く道)間を結んだ峠で山頂にはお宮や数件の廃屋がありました。記憶に乏しかった祠峠を確認できて良かったです。新道に石仏群がありましたが、旧道にあったものを村の衆が一カ所にまとめたものと思います。古宿は奈川に4カ所あった宿屋の一つですが面影はありませんでした。
2016年11月05日
野麦街道(寄合渡~旧街道口、ワサビ沢)
2 コース 寄合渡宿ー保平ー川浦宿ー野麦ワサビ沢
3 所要時間 2時間30分 約8㎞
(クリックして大きくして見てください)
寄合渡から野麦峠に向かって、神谷集落、保平集落と続きますが、保平は昔から信州の伝統野菜「赤かぶ」栽培で有名です。お年寄りに保平かぶについて訊ねましたら「赤かぶいるかい、いるならやるよ」と気を使わせてしまいました。保平には六地蔵と馬頭観音の石仏群が祀られており古い集落だと思いました。野麦街道最後の集落「川浦」は、飛騨高山と繋がりが深く交流が活発に行われていました。川浦は工女の定宿「宝来屋」があり宿泊者全体の6割を占めていたとのことです。冬季は積雪も多いため雪固めや案内などで川浦衆の苦労は相当多かったと思います。六地蔵と馬頭観音の石仏群がここにもありました。毎年5月には、女工さんたちを偲んだ野麦峠まつりが開催されています。冬季間は道路が閉鎖されます。
2016年11月01日
野麦街道(古宿~黒川渡~寄合渡宿)
2 コース 奈川支所~古宿~黒川渡~太平~寄合渡宿
3 所要時間 1時間30分 約5㎞
(クリックして大きくして見てください)
「右ハひだ、左ハやぶ原」
奈川支所、古宿を経由して旧役場があった黒川渡から上流へ向かって野麦街道を歩きました。錦織成す紅葉が広がっており最盛期を迎えていました。この美しさは古今東西、変わらぬ自然の恵みであり、往時の人々も眺めていたと思うと懐かしあさがこみあげてきました。しばらく歩くと奈川太平の石仏群があり、馬頭観音、大日如来、六地蔵が祀られていました。さらに南の奈川寄合渡は、飛騨、藪原、松本の分岐点で番所が置かれていましたが、今は看板のみでした。道標には「右ハひだ、左ハやぶ原」と刻まれており街道の面影が残っていました。奈川寄合渡には氏神の天空大明神が祀られており、9月第一土曜日には無形文化財の獅子舞が奉納されるとのことです。勇猛果敢な獅子退治の舞とのことで一度見てみたいと思いました。
2016年10月27日
野麦街道(新島々~橋場番所)
2 コース 上高地線新島々駅ー大野田ー竜島ー橋場
3 所要時間 1時間30分 約5㎞
(クリックして大きくして見てください)
断崖崩落の危険で通行止め
野麦街道は上高地線の松本電鉄新島々駅から上流の大野田を経て、旧波田町竜島を通っていましたが、竜島地域はほとんどの人が他地域に移住してしまい、住んでいるのは1名になってしまいました。原因は生活基盤の変化にあったと思いますが、国道158号線が梓川左岸に敷設されたこと、東京電力竜島発電所が無人になったこと、在地の背後が山で手前が梓川で耕地が少ないこと、公共交通機関もないなどが重なって集落崩壊につながったと思います。道は文化の発祥であり野麦街道の痕跡が失われていくことが口おしかったです。しかし、生活環境の良い所へ向かうのも、また必然性かも知れません。竜島はかつて上流の橋場集落ともつながっていましたが、これも竜島地籍で断崖崩落の危険がありとのことで通行止めになっていました。
2016年10月25日
野麦街道(鵬雲崎~橋場番所)
2 コース 鵬雲崎~稲核風穴~稲核~橋場番所
3 所要時間 2時間 約7㎞
(クリックして大きくして見てください)
国道158号の東京電力三殿ダム上流に梓川の渓谷が美しい「鵬雲崎」があります。この地に野麦街道の面影漂う馬頭観音がありました。険阻な断崖上の山越えであり苦労が多かったと思います。稲核集落には風穴が何カ所もあり、かつては天然の冷蔵庫として県内外の蚕種冷蔵用などに利用されていました。稲核から先の街道は梓川右岸にありましたが、すでに廃道になっています。安曇支所がある徳本峠入口近くの橋場集落は、松本藩が口止め番所を置いた場所で、梓川の天然の岩盤上に刎橋構造の「雑炊橋」を架けました。どんな洪水にも流されることはなかったとのことで、信濃の国の安曇郡と筑摩郡をつなぐ要衝地でした。現在は斜張橋の橋になっていますが、雑炊橋は恋伝説「お節」と「清兵衛」が雑炊を食べて質素倹約したことがきっかけで橋が架かり名前がつけられたとのことです。橋のたもとに「後の世の人の為ともなりにけり恋故かけし谷川の橋」と謳われた石碑がありました。
2016年10月25日
伊那街道(伊那部宿~宮田宿)
2 コース 伊那市駅~伊那部宿~沢渡駅~宮田宿
3 所要時間 5時間(見学、休憩含む) 約10㎞
(クリックして大きくして見てください)
伊那部宿は飯田城下と塩尻宿の中間に位置し、伊那市駅から少し歩いたところにあります。江戸時代に2度の火災にあったため、火災を免れた豪農「井澤家」を除けば宿場の面影は少なかったです。規模は南北に330mに及んでおり、枡形や町屋の形態は留めていて様子は十分理解できました。発足20年が過ぎた「伊那部宿を考える会」の活躍は素晴らしく、旧井澤家住宅の復元活動、案内板や標柱の設置、史跡マップ作り、イベント行事などが活発に行われていて、地域の宝や文化を守ろうとする情熱に感動しました。当日は婦人部の皆さん手作りの、おはぎ、ひじきの煮物などのご接待をいただき、心温まる人情に触れる思いでした。伊那市小出石仏群は、伊那街道沿線で見かける冬の念仏講「寒念仏供養塔」が、伊那市下島の薬師堂や宮田村宮田宿には馬頭観音、庚申塔などの石仏がたくさん残っていました。中山道の脇往還だけあって中馬稼業で繁栄した様子や、庶民の生活文化を石仏を通じて味わうことができました。宮田宿は宿場の面影が薄かったです。(善光寺街道協議会主催 参加者35名)
2016年10月11日
北国街道(追分宿~小諸宿)
2 コース 追分宿分去れ~馬瀬口~平原~小諸宿
3 所要時間 5時間 約14キロ
(クリックして大きくして見てください)
十念寺跡に踊念仏の一遍上人碑
追分宿の去れから右手に雄大な浅間山を仰ぎながら標高差200メートルを下って小諸宿をめざしました。御代田町馬瀬口は古い家並みが残っていて往時の面影がありました。馬瀬口は朝廷に馬を納めた牧で、柵口(ませぐち)神社と長泉寺に馬頭観音や馬立像などがあり名残を感じました。御代田町と小諸市の堺の浅間山南西麓は、両岸が垂直に削られた「田切地形」となっています。深い侵食が幾筋もでき、谷底は平坦で田畑になっています。何気なく見ていた風景でしたが、あらためて地域独特の地形を歩いて眺めることができました。小諸市平原の十念寺跡には踊念仏の一遍上人の碑が建っていて、毎年3月に実施している来迎会に使われる仏面は室町時代のもがあり演技の所作は平原独特のものらしいです。踊念仏は仏教的演技の一つで一度見たいと思いました。小諸駅そばの乙女坂に甲州道道標があり、古碑には右甲州道・左江戸海道と刻まれていました。佐久甲州道は佐久、野辺山を経て韮崎宿に至る街道ですが確認できて嬉しかったです。
2016年10月08日
北国街道(岩鼻~坂木宿)
2 コース 西上田駅~岩鼻~鼠宿~坂木宿
3 所要時間 2時間15分 約7㎞
(クリックして大きくして見てください)
身にしみて 大根からし 秋の風
しなの鉄道、西上田駅の北に難所の「岩鼻の嶮」があります。岩鼻は上田領と松代領の境界で崖下を千曲川が迫り垂直の壁になっています。街道は崖の中腹を迂回していたとのことですが、加賀藩の参勤交代では、ここを無事通過すると金沢の国許まで使いを走らせたと言われています。岩鼻から間もなく珍名の宿場「鼠宿」があります。幕府公認の宿場ではなく松代藩の私宿でしたが、後に上田宿と坂木宿の中間にある間の宿として栄えました。国道18号線沿いのため面影は少なかったですが、鼠の名前が付いた交通信号機や地区名が残っていて昔日の感を味わいました。坂城町中之条西念寺には松尾芭蕉が詠んだ「身にしみて 大根からし 秋の風」の句碑があります。坂城町はねずみ大根の特産地で「おしぼりうどん」の漬け汁として有名ですが、もう少し時期が遅かったら味わえたのにと残念に思いました。
2016年09月27日
伊那街道(松島宿~伊那坂下の辻)
2 コース 伊那松島駅~松島宿~北殿大泉宿~
常円寺坂下の辻道標~伊那市駅
3 所要時間 約5時間(見学含む) 約12キロ
(クリックして大きくして見てください)
(名匠 守屋貞治作)
街道は国道153号線を何回も横断するがほぼ沿線上にありました。松島宿は敵の進入を防ぐ鍵の手は残っておりましたが宿場の雰囲気はなかったです。印象に残ったのは、箕輪町法界寺の高遠の稀代の名匠守屋貞治作の傑作石仏、地蔵菩薩像でした。貞治は仏門に帰依し石仏を掘る時は、香を炊き念仏を唱えながら彫像に励んだとのことです。個性的で精神性を感じる石仏が貞治の特徴と聞きましたが、上諏訪の諏訪家の菩提寺「温泉寺」に多くの石仏が残っています。全国的に活躍した高遠の石工は、高遠藩が税収増加をねらって「旅稼ぎ石工」を奨励したことから、北は青森、南は山口の1都18県におよんだようです。伊那市の北殿大泉宿は北殿村にあった東側6軒に、大泉村から移転した6軒が西側に住居してできた合宿(あいのしゅく)でそれぞれに問屋がありました。伊那市駅の近くに常円寺坂下の辻道標がありました。善光寺街道、権兵衛街道(はびろ道)、高遠への分岐道標で、重要な分去れです。 善光寺街道協議会主催 参加者32名。