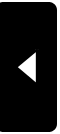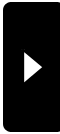2019年05月09日
北国街道東脇往還(松代道)てくてく旅(須坂市福島宿~長野市長沼宿)
2 コース 須坂市福島宿~村山橋~長沼宿
3所要時間 1時間45分 約4㎞
(クリックして大きくして見てください)
 長沼宿・南入口の桝形
長沼宿・南入口の桝形-s.jpg) 長沼宿・本陣(西島家)
長沼宿・本陣(西島家)福島宿(須坂市)と長沼宿(長野市)間は、かつて千曲川の「布野の渡し」(柳原)を渡っていました。現在は鋼鉄の橋、村山橋を渡り堤防沿いに長沼へ行きます。長沼宿南入口に宿場独特の桝形が残っていました。10mほどの小高い土塁上に秋葉社を始めとする4基の石詞が祀られています。長沼は平安時代から有力な豪族が治めており、北側が城下町、南側が宿場町の顔として存在していましたが、現在はリンゴ畑になっていて城下町としての面影はまったく無く城址跡に大きな欅と碑がある程度です。南側の宿場町は旅籠がなく本陣が旅籠を兼ねており本陣の西島家には長屋門の面影が、問屋を努めた向かいの丸山家の門には天井部分に往時の駕籠が保存されており宿場風情は感じられました。印象深かったのは林光院門前にあった道標「右ハゑちこ道 左ハせんく王うし道」と刻まれていた江戸中期の古碑でした。小さな道標でしたが懐かしさと優しさを感じました。
2019年05月06日
北国街道東脇往還(松代道)てくてく旅(長野市川田宿~須坂市福島宿)
2 コース 長野市川田宿~川田領家~綿内追分~須坂市福島宿~村山駅
3 所要時間 3時間45分 約9㎞
(クリックして大きくして見てください)
 川田宿・火防の神下組秋葉社
川田宿・火防の神下組秋葉社 川田領家・自然石に据えられた秋葉社
川田領家・自然石に据えられた秋葉社長野電鉄須坂駅の駐車場に車を停め屋代行きバスに乗車し川田駅で下車しました。
川田宿の西端に下組秋葉社が安置されています。この秋葉社は高さ2.5m位の自然石の上に据えられており火防の神として宿場を守っています。同じような高さの祠が隣接地の川田領家にもありました。高い所に据えられているので違和感を覚えましたが、実は川田宿は宿場が定められてから五度にわたり千曲川の水害に遭い宿場の位置が変遷したとのことです。秋葉社も水害から守るため高い位置に祀られるようになったと推察しました。福島宿は東脇往還と大笹街道が交差し、 千曲川通船「布野の渡し」もあり交通の要衝として栄えました。本陣兼問屋の竹内家、丸山家の入口の長屋門と両脇の荷蔵は見事で荷物の取り扱いが多かったことを物語っています。布野の渡し(柳原)は北国街道の矢代、丹波島が川留めになっても流れが緩やかだったため川留めにならず別名「雨降り街道の渡し」と言われていたとのことです。このため特に雨の日の福島宿は旅人たちで賑わっていたとのことです。福島宿北端に三面六臂馬頭観音がありますが、大変珍しい像容で県内街道歩き千キロ踏破した中では3カ所目の発見でした。須坂市のお宝石造物と言って良いと思います。
続きを読む
2019年05月04日
北国街道東脇往還(松代道)てくてく旅(長野市松代~川田宿)
2 コース 長野市松代~荒神町道標~鳥打峠~禅福寺~関崎の渡し跡
~川田宿
3 所要時間 2時間45分 約7㎞
(クリックして大きくして見てください)
松代藩七渡し一つの常夜燈
 川田宿、本陣兼問屋(西澤家)
川田宿、本陣兼問屋(西澤家)長野電鉄松代駅に車を停め令和初のてくてく旅に出かけました。松代の城下町は町八町と呼ばれる町割りで西の博喰町から北の荒神町までを町八町と呼んでいます。北国街道東脇往還(松代道)は荒神町追分から北東へ進み山間を縫うように行きます。追分に昭和初期に建てられた道標碑があり、左…長野市、右…須坂、中野町と刻まれていました。街道は緩やかな坂道で新緑を味わいながらの峠越えでした。松代藩の刑場跡と言われる鳥打峠を越えると飯縄山、妙高山、高妻山、後立山連峰が現れ残雪の美しい山脈を仰ぎ見ることができました。街道は高速道路と並行しており右手の山際に、屋根に六文銭の紋が入る禅福寺の重厚な本堂が、さらに進むと川田宿と川中島平を結ぶ関崎の渡し跡があります。この渡しは松代藩七渡しの一つで常夜燈が往時の賑わいを偲ばせていました。川田宿は典型的なコの字形を示し、中央に本陣兼問屋(西澤家)、東西に火防の神である秋葉社に守られ古い宿場町の面影を留めていました。
2018年11月13日
秋葉街道てくてく旅信州編(飯田市南信濃小嵐~青崩峠下)
2 コース 飯田市南信濃小嵐~青崩峠~浜松市水窪町塩の道碑
3 所要時間 3時間30分(昼食、休憩含む) 約6㎞
4 主 催 遠山郷やらまい会
5 参加者 約100名
(クリックして大きくして見てください)
両側に畑の石積みが残る秋葉街道
左右の 石の色が違います。右は中央構造線の青崩れを表現
飯田市南信濃と浜松市水窪町を結ぶ青崩峠(1,082m)の古道(秋葉街道・青崩峠古道)約6キロを歩く催しが地元の「遠山郷やらまい会」主催で実施されました。
南信濃和田宿から青崩峠下・塩の道碑までの古道は、約12㎞ありますが、中間点の市道南信濃156号線ヒヨー越分岐の小嵐地区(馬宿の旧島畑付近広場)から峠に向かって出発しました。街道の標識は、地元の皆さんの努力によって各所に設置されており、道も支障のない程度に整備されていました。古道ルートで特に印象に残ったのは、飯田市南信濃小嵐の判之木集落跡と茶屋跡、さらには両側に畑の石積みが残る街道の面影でした。また青崩峠山頂からの谷地形の遠州一望と馬頭観音石仏、青崩神社が印象に残りました。
青崩峠は信州と遠州の国境峠で峠は中央構造線の大断層沿いにあり、青色を呈する軟弱な岩盤にちなむ名称とされています。かつては秋葉神社詣での信仰の道として、日常生活の物資輸送の道として、戦国時代は武田信玄の遠州、三河への南攻の道として往来が盛んで歴史、文化、経済に大きな影響を与えた峠です。飯田線が開通すると道は衰退し往来する人も少なく寂れました。
2018年11月07日
大笹街道てくてく旅信州編(須坂市福島宿起点道標~仁礼宿)
2 コース 下り歩き
須坂市仁礼宿馬頭観音~八丁鎧塚古墳~須坂市福島宿起点
道標~長野電鉄村山駅
3 所要時間 約3時間 約10㎞
(クリックして大きくして見てください)
 須坂市「八丁鎧塚古墳」
須坂市「八丁鎧塚古墳」「右 松代道 左 草津仁礼道」
大笹街道仁礼宿へは、長野電鉄バスを利用し須坂駅から湯っ蔵んど下の旧街道入口まで乗車し向かいました。仁礼宿の馬頭観音は県下有数の大きさで新しい注連縄が張られており、祭礼に対する地域の姿に接し日本の心を見る思いがしました。ここから鮎川右岸を北西に向かって下りましたが少し行くと「右 すさか 左 ぜん光寺」の道標がありました。往時の須坂と善光寺を示す道標で大笹街道はここを左折し川の右岸側を通っていました。しばらく行くと「道が途切れているよ」と地元の人に教えていただき戻って新道を歩き右岸側に戻りました。しばらく川沿いを歩くと県指定史跡の「八丁鎧塚古墳」があり東日本最大級・最古級と書かれておりましたが、過去に見たことのない積石塚でした。ここから福島宿へは、道祖神や道標などを確認し国道沿いを歩きました。福島宿は北国街道東脇往還(松代道)と大笹街道が交差する宿で、千曲川の船着き場もあったため、交通の要衝として栄え面影が色濃く残っていました。勝楽寺のそばに大笹街道の起点を示す道標があり「右 松代道 左 草津仁礼道」と刻まれていました。
大笹街道とは(仁礼会発行 大笹街道ガイドより)
江戸時代、善光寺平と上州を経て江戸を結ぶバイパスとして物資輸送の重要な脇街道だった。江戸末期には、善光寺詣でや草津温泉への湯治、大谷不動尊・米子不動尊詣での旅人の往来する街道だった。「大笹街道」の名称は、上州大笹(群馬県嬬恋村大笹)に至るところから呼ばれたもので、上州側からは「仁礼街道」あるいは、「信州街道」と呼ばれていた。
2018年10月09日
佐久甲州街道てくてく旅信州編(佐久市臼田宿、野沢宿、岩村田宿)
2 コース 佐久市青沼駅~臼田宿~野沢宿~岩村田宿
3 所要時間 約6時間(見学、休憩含む) 約12㎞
見学場所 龍岡城址、ピンコロ地蔵、旧中込學校
(クリックして大きくして見てください)
 龍岡城址・五稜郭
龍岡城址・五稜郭佐久市内3宿場の臼田、野沢、岩村田は、佐久地方の政治、経済、文化の中心地で、中山道、佐久甲州街道、下仁田道、善光寺道など主要街道の分岐点で米の集散地として物資輸送の要衝地でした。建造物からも豪族、豪農、豪商の面影が随所で見られました。宿場で特に印象に残ったのは、臼田宿では江戸初期に名主を勤め、後に、代官巡視の際の宿泊所になった県宝・井出家、野沢宿では宿場の中心にあった「女男木」の欅と樹下の道標「北木曽路・東岩村田道・南甲州道」の存在感でした。岩村田宿では住吉道標「従是善光寺」の南から始まる佐久甲州街道との分岐石碑で、往時の面影を十分感じました。
(臼田宿)
野沢宿と高野町宿の間の宿。中心集落の臼田は千曲川西岸にあり、佐久甲州街道沿いに市街地を形成、南佐久の政治、経済の中心地として発達した。
(野沢宿)
中世の伴野荘の地で、江戸時代佐久甲州街道の宿場町、佐久盆地南部の米の集散地で豪農、豪商が住んでいた。
(岩村田宿)
中世の大井荘の地で、江戸時代岩村田藩の陣屋町であった。中山道、佐久甲州街道、善光寺道、下仁田道の分岐点で米穀の集積地として物資輸送の要衝地。交通、政治、文化、産業の盛んな宿場町。
2018年09月17日
佐久甲州街道てくてく旅信州編(佐久穂町・上畑宿、高野町宿)
2 コース 佐久穂町大石川橋の一里塚~JR八千穂駅~上畑宿、
中畑、下畑~高野町宿~宿岩~JR青柳駅
3 所要時間 約3時間30分(休憩含む) 約9㎞
(クリックして大きくして見てください)
佐久穂町八千穂大石川橋の一里塚を出発。この一里塚は佐久甲州街道と麦草峠の北にある大石峠を越えて茅野に通じる旧道(大石峠道)の分岐点で、説明看板があり大きな榎が往時を偲ばせていました。この先、約0.5キロ北に上畑宿がありますが、途中寄り道をしJR八千穂駅そばにある奥村土牛記念美術館と銘酒「井筒長」の黒沢酒造「酒の資料館」を見学しました。
(上畑宿)
上畑の八千穂保育園前に「畑八村道路元標」があり隣に上畑宿の由緒説明があり大変参考になりました。宿場は江戸時代寛保2(1742)年の大洪水(戌の満水)によって壊滅的な被害を受け山際の高台に移転しました。流失家屋140軒、死者248名(全人員の半分)の大被害でした。宿場は余地峠を越えて上州に至る余地峠道や茅野へ向かう大石峠道の結節点で問屋場がおかれ人馬の「継ぎ立て」で賑わっていました。旅籠や茶店も多数ありましたが、今は宿場の雰囲気をとどめる程度でした。
(高野町宿)
上畑宿から北へ約4キロ行った所に高野町宿があります。ここは陣屋がおかれ問屋場を中心に荷物や人馬の往来が激しく240戸が軒を並べていたとのことです。千曲川を渡って余地峠・十石峠を経てそれぞれ上州・武州に通じる拠点の宿場でした。現在は陣屋跡に説明案内はありますが面影はありません。宿場は旧家の連なりなどから雰囲気を感じとることはできました。
2018年09月13日
佐久甲州街道てくてく旅信州編(小海町)
2 コース 海尻宿(南牧村)~小海駅~八千穂駅(佐久穂町)
3 所要時間 約4時間 約12㎞
(クリックして大きくして見てください)
JR小海線海尻駅を出発。南牧村海尻宿の北に甲斐の国・武田氏による信濃侵攻の前進拠点の海尻城址入口が天台宗醫王院の境内にありました。この先の小海町八那池へは海尻洞門を抜けますが、かつては深山断崖をへばりつく人馬を阻む佐久甲州街道最大の難所でした。千曲川の東岸は古生代の古い地層で水害に遭うことは一度も無かったようですが、西岸は八ヶ岳が噴火した際の比較的新しい地層で国道沿いに断層がむき出しになっています。水害もあり街道は迂回したとのことです。小海の名前は887年八ヶ岳(天狗岳)が水蒸気爆発し大崩落した時、小さな湖ができ起源となったと伝えられています。その時を知る埋もれ木が役場ロビーに展示されていました。さらに役場のそばの北牧小学校入口向かい側には、移されていた馬流の一里塚がありました。この区間は旧道が所々に残っていて馬頭尊、庚申塔の石造物が残っていました。
2018年07月12日
佐久甲州街道てくてく旅信州編(南牧村・海ノ口宿、海尻宿)
2 コース 野辺山駅~海ノ口馬市場跡~海ノ口宿~海尻宿
3 所要時間 約4時間 約11㎞
4 佐久甲州街道とは 韮崎宿~岩村田宿 総距離 約80㎞
(クリックして大きくして見てください)
佐久甲州街道・信州編 海の字が付く宿場・海ノ口宿、海尻宿
JR野辺山駅で佐久甲州街道・海ノ口宿について情報収集をし出発しました。国道141号線を北へ約4キロ行った所に海ノ口馬市場跡があります。南牧村は江戸時代から農耕馬、乗馬の一大産地となり、南牧の牛馬市は900頭を超え,木曽に次いで賑わったとのことです。村名も南牧と付けられました。この先のレストラン141の所に旧国道141号と現国道141号が分岐する所があります。
旧道が佐久甲州街道の道筋にあたり南牧村本村の海ノ口宿へと続きます。宿場は野辺山原の裾の谷間にあり荷物の継立、旅人の休息,宿泊として賑わっていました。家並みや坂道の古道から宿場の雰囲気は十分に感じられました。4キロ先の海尻宿にも問屋が置かれ往時の面影が残っていました。二つの海の宿場名の由来は、平安時代(887年)に八ヶ岳が水蒸気爆発を起こし、泥流によって塞がれた千曲川に天然ダム湖が誕生したことによります。やがてこのダム湖も大崩落し消滅しましたが、天然ダム湖に千曲川が流れ込んだ場所を「海ノ口」、反対側の流出部を「海尻」と呼ばれました。
「白樺・青空・南風、こぶし咲くあの丘……」で始まる名曲「北国の春」の作詞者・いではく(作曲は遠藤実)は、南牧村出身で佐久高原を良く表現しています。いでの生誕地の海尻の国道沿いに歌詞記念碑があります。
2018年06月30日
佐久甲州街道てくてく旅信州編(南牧村・平沢宿)
2 コース 野辺山駅~平沢峠~平沢宿~清里駅
3 所要時間 約3時間30分 約9㎞
4 佐久甲州街道とは 韮崎宿~岩村田宿 総距離 約80㎞
(クリックして大きくして見てください)
佐久甲州街道・信州編
出発地のJR小海線野辺山駅は、標高1,345メートルで眼前に八ヶ岳連峰を仰ぎ駅周辺の野辺山高原は、高原野菜の産地として脚光をあびております。かつてこの野辺山原は高冷地で3里余の原野は無人の荒野で佐久甲州街道(佐久往還)屈指の難路でした。駅から南へ30分歩くと野辺山宇宙電波観測所があります、その近くに三軒屋跡がありました。三軒屋とは茶屋跡で徳川幕府が行旅人が雨雪を避難できるよう移設し救護にあたらせた場所で往時の難路を偲ばせる所です。この先の平沢峠は、佐久甲州街道ただ一つの峠で頂上に立つと八ヶ岳連峰、甲斐駒ケ岳などが聳えますが、天候に恵まれず仰ぎ見ることはできませんでした。ただニッコウキスゲが最盛期を迎えており飯盛山を往復するハイカーも大勢いました。さらに先の海ノ口城主平賀源心の胴塚碑周辺は平沢古道の面影が残っていました。草木に覆われ足を踏み入れる余地はありませんでした。平沢峠を下ること約1時間30分すると南牧村平沢地区になります。かつての信州7宿最南端の平沢宿場です。山梨県かと錯覚を覚えるほど県南に位置し高原野菜御殿が林立していました。宿場の面影は薄く村中の道祖神と筆塚遺構がかつての面影を留める程度でした。往時は塩を始め材木などの物資輸送や善光寺詣り、身延山詣り、伊勢参りの休憩宿として存在感がありました。
2018年05月31日
秋葉街道てくてく旅信州編(遠山郷・上町宿~和田宿)
2 歩きコース 遠山郷(飯田市南信濃)上町宿~木沢~和田宿
3 所要時間 約3時間 約10キロ㎞
4 車コース 和田宿~梁木島番所 約3㎞
(クリックして大きくして見てください)
遠山氏の菩提寺「龍淵寺」
遠山郷の上町宿は、宿場の中央に秋葉・琴平の石碑や屋号看板が残っており街道の面影がありました。木沢宿(間宿)は上町宿と和田宿の中間にある宿場で、木沢八幡神社では霜月祭りが行われ、街道には旅人を見守った常夜燈がありました。
和田宿は天竜村、浜松市水窪方面の出入口宿場で、遠山郷では一番の賑わいがあった宿場です。「飯田行くなら馬糞を見ろ」と言われるほど馬の通行が多かったとのこと。街道の雰囲気は、商工会議所遠山郷支所の秋葉・金毘羅大権現碑から下市場諏訪神社間に面影が残っておりました。なかでも中程にあった下和田道標には「此方右三ツ嶋(満島)左あきは道(文政11年)」と刻まれ、「遠山(満島)街道」と呼ばれ、天竜川の水運を使って満島に下された塩などの物資が、大量に遠山郷へ運び込まれたとのことです。和田の龍淵寺は遠山の中心的寺院でかつて遠山郷を治めた遠山氏の菩提寺として創建された寺です。
2018年05月28日
秋葉街道てくてく旅信州編(遠山郷・程野~上町宿)
2 歩行コース 遠山郷(飯田市上村)程野~中郷~上町宿
3 所要時間 約3時間 約10㎞
4 車コース 地蔵峠~程野、 上町宿~下栗
(クリックして大きくして見てください)
大鹿村、飯田市上村境の地蔵峠から飯田市上村程野の秋葉古道(ソラ街道、大平道)は、ほとんどが廃道のため市道4号線を車で程野まで下りました。
遠山郷(飯田市上村)程野地区は国道152号に沿っており、秋葉街道の程野正八幡宮は霜月祭りが行われ参道口に秋葉大権現と金毘羅大権現(水難防止)の石碑が建っていました。上町宿は小川路峠から飯田に至る秋葉街道の一方の玄関口で遠山谷の秋葉街道出入口の集落になり
ます。集落には馬宿6軒、旅籠3軒、商家10軒があったとのことです。国無形民俗文化財の上町正八幡宮の霜月祭りは、約800年の歴史があり神々に湯を献じ新たな年の生命再生を願う湯立神楽の神事が神面の舞とともに夜を徹して行われています。遠山郷は飯田市上村・南信濃で古くから呼ばれており、厳しい自然の中で神の存在を感じながら生きてきました。
2017年11月04日
伊那街道てくてく旅(松源寺~飯田城赤門)
2 コース 市田駅~松源寺~瑠璃寺~市田宿~飯田城赤門
3 所要時間 3時間 約8㎞
(クリックして大きくして見てください)
NHK大河ドラマ「おんな城主・直虎」の許婚、直親(亀之丞)が、今川氏から命を狙われたため落ち延びた高森町の松源寺を見学しました。ドラマ開始以来、各地から大勢の人が訪れており当日も売木村から30人ほどが来て見学していました。寺に続く松岡城は、竜東地域が一望できる要害堅固な城で、亀之丞もこの景色を眺め井伊谷へ帰郷する日を夢見ていただろうなと思いました。
高森町の瑠璃寺は源頼朝の祈願所となり寺領750石が永代寄進されました。その際3本の桜が共進され桜の名所になっています。古刹の雰囲気が漂っており伊那谷にこれほどの名刹があったことを初めて知りました。春にはもう一度訪ねたいところです。高森町の市田宿は、旧153号線に面しているため時代の変化が激しく面影は薄かったです。
終着地の飯田城址には唯一の現存建造物・赤門(旧飯田城桜丸御門)があり市の有形文化財に指定されています。赤門(朱塗り門)は、大名が徳川将軍家の姫を正室に迎える時だけ設置が許されたとのこと。
伊那街道歩きは2年間の旅路でしたが、天候に恵まれ主催者の名ガイドもあり中馬街道の歴史、文化を十分楽しむことができました。
2017年10月31日
伊那街道てくてく旅(片桐宿から本学神社)
2 コース 上片桐駅~片桐宿~大島宿~本学神社~下平駅
3 所要時間 約3時間30分(昼食、見学含む) 約8㎞
4 主 催 善光寺街道協議会 参加者18名
(クリックして大きくして見てください)
台風22号一過の晴れに恵まれ、稀に見る好条件で街道歩きをしました。
中央自動車とJR飯田線に挟まれた、県道15号(旧国道153号線)の飯島飯田線が街道の道筋になります。宿場は飯田藩による伝馬制によって整備されましたが、片桐宿、大島宿は面影が薄かったです。道中、見学をした天台宗(法華経を経典とする仏教で最澄が開いた宗派)のお寺、瀧泉寺、光明寺でご接待をいただきました。元善光寺へ向かう行脚に「実際に体験をしなければ得られない功徳を自分のものにしてほしい」と身に余るお言葉とおもてなしをいただき恐縮しました。大島宿の北のはずれに大島の一里塚がありましたが、飯田を起点にした一里塚で飯田から三里にあたります。五街道以外の一里塚は珍しいなと思いました。
高森町では日本で初めて、国学の四大人(しうし)「荷田春満・賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤」を祀った本学神社を参拝しました。受験シーズンには合格祈願に多くの人が訪れるようです。
街道は秋の気配が漂い、長野県初の地域農産物ブランド「市田柿」がたわわに実っていました。
2017年10月13日
初期中山道てくてく旅(小野宿~三沢峠~岡谷)
2 コース 小野駅~小野宿~しだれ栗~三沢峠~鶴嶺公園~岡谷駅
3 所要時間 約6時間(旧小野家住宅、旧林家住宅見学等を含む)
通常所要時間約4時間 距離約9㎞
4 主 催 NPO法人木曽川・水の始発駅 参加者28名
(クリックして大きくして見てください)
右をの 左みさは
小野宿から岡谷へ向かう初期中山道は、しだれ栗森林公園へ行く道がほぼ街道のルートになります。途中、右手に楡沢の一里塚がありますが、原型を留めており二つの塚の間に当時の道筋をしのぶことができます。(江戸日本橋より数えて58番目)しだれ栗の自生地は他に例を見ない光景ですが、しだれは火山活動による突然変異とか。森林公園を過ぎてから道がカーブした地点に小野峠を示す石碑があり、右折して80メートル先に小野峠(三沢峠)があります。ここから先は未舗装の下り歩きになりますが結構荒れていました。さらに下るとツツジの名所「鶴嶺公園」があります。シルクエンペラー片倉寄贈のツツジで春には3万株の花が咲き乱れ大勢の見物客で賑わいます。その下に三沢の一里塚(江戸日本橋より57番目)があり岡谷の市街地へと進んでいきます。初期中山道開削ルートは、暴れ天竜川を避けた山手ルートで川の氾濫を避けた物資輸送ルートであったことがよくわかりました。馬頭観音菩薩の石仏群も結構ありました。
2017年09月14日
初期中山道(小野街道)てくてく旅(塩尻市桜沢~辰野町小野宿)
2 コース 塩尻市桜沢~牛首峠~前山一里塚~小野宿
3 所要時間 3時間30分 約9㎞
(クリックして大きくして見てください)
(江戸日本橋より60里)
中山道には塩尻を通らない初期の中山道がありました。塩尻市桜沢(旧楢川村)から東の山中に入り、牛首峠を越えて小野宿、三沢峠(小野峠)を経て岡谷へ至る街道です。権兵衛峠が開くまでは、伊那と木曽をつなぐ唯一の道で小野宿からは小野街道を利用していました。岡谷市、塩尻市、辰野町が協議会を作り作成したマップが参考になります。今回は桜沢から小野宿まで歩きましたが、小野側は、馬頭観音、道祖神、庚申塔、一里塚などが整備されており往時の雰囲気を十分に味わうことができました。10月には枝垂栗から三沢峠を越え岡谷へ行きます。
2017年09月03日
秋葉街道てくてく旅信州編(大鹿村・鹿塩~大河原大鹿歌舞伎大磧神社)
2 コース 秋葉古道鹿塩散策ー中尾峠ー大河原大磧神社
3 所要時間 3時間30分 約8㎞
(クリックして大きくして見てください)
大鹿村の秋葉街道歩きは最終回です。大鹿村中心地の鹿塩から大河原へ向かう旧道歩きの旅でした。鹿塩の塩川橋を渡ると間もなく秋葉古道の標識が目につきます。古道は草に覆われており一部は歩くことは出来ますが、ガイドなしでは不安のため旧道のアスファルトを歩きました。大鹿村鹿塩河合には自治会が所有する「夜泣き松」があり、目通り4.6メートル、推定樹齢700年の立派なアカマツ。「県内では注目すべき巨木であることに加え、古くから信仰の対象で文化的価値が高い」として、今年、県天然記念物に指定される予定です。大鹿村に名物が一つ増えますが、枝ぶりが見事で圧倒されました。街道沿いは急傾斜地が多く民家が点在しています。古老曰く「洪水の危険を避けるため街道、民家は川沿いではなく山側を利用した。裕福な家ほど高台にあった」とのこと。街道が山間にある理由が良く理解できました。大河原では春に大鹿歌舞伎が開催される大磧神社を訪ねました。舞台は歴史を感じる趣があり地歌舞伎を見てみたいと思いました。
2017年08月28日
秋葉街道てくてく旅信州編(大鹿村、大河原~安康露頭~地蔵峠)
2 コース 下り歩き
地蔵峠ー安康露頭ー深ヶ沢ー大沢橋ー小河原小渋橋
3 所要時間 下り3時間30分 約13㎞
(クリックして大きくして見てください)
大鹿村の秋葉街道第3弾は、飯田市上村境の地蔵峠から大鹿村最大の平坦地大河原の中心部へ向かう下り歩きの旅でした。地蔵峠は信州百名山「鬼面山」の登山口になっておりこの日も4台の車が停まっていました。上流部安康地区(安康とはカジカのことらしい)には、本州を縦断する中央構造線の断層「安康露頭」が川に面して露頭していました。その下流の深ヶ沢地区は、明治の頃に入植した集落があったとのことでしたが面影はありませんでした。峠から大沢橋までの約10キロ区間は、36災害の影響で古道は失われ新道の車道歩きでした。秋葉街道沿いの引の田集落に入ると国指定重要文化財の松下家住宅があり何故か安心感が湧きました。小さな集落ですが、代々名主をつとめた家で切妻造りで200年が経過しています。谷間の中に歴史の生き証人が残っていたことが驚きでした。大鹿村中心部から地蔵峠を越えて遠山郷への道は、距離があり山越えのため旅人は相当苦労しただろうなと思います。
2017年08月15日
秋葉街道てくてく旅信州編(柄山災害記念碑~市場神社大鹿歌舞伎舞台)
2 コース 柄山災害記念碑ー女高ー儀内路ー小塩ー鹿塩、市場神社
3 所要時間 下り歩き 3時間 約10キロ
(クリックして大きくして見てください)
大鹿村の秋葉街道第2弾は、北川露頭の下流、柄山・災害記念碑から大鹿村の中心部へ向かう旅でした。村の上流部鹿塩川流域の北川地区は、伊那谷を襲った36災害の爪痕が癒えず山肌がいまだにむき出しになっているところがあります。村々の変化は激しく、女高集落は13年前の平成16年に12戸あった集落が廃屋状態に、その下の儀内路も過疎化が進んでいました。中間点の小塩地区に入るとようやく国道が2車線化し生活の匂いがしました。
「鹿塩」は、鹿が好んで舐めるという湧き水を飲むと塩分を含んでいたことが地名の語源になったとのこと。鹿塩の市場神社は、国選択無形民俗文化財大鹿歌舞伎が公演されているお宮です。昭和58年より毎年秋の公演が10月第3日曜日に行われています。来場者は1,500人を数え村の人口の1.5倍になる盛況ぶりとか。隔絶されたかに見える山間地ですが、秋葉街道を通じてさまざまな文化が入ってきたことが伺えました。
2017年08月13日
秋葉街道てくてく旅信州編(大鹿村・分杭峠~北川露頭下)
2 コース 分杭峠ー三ツ沢ー矢立木ー北川露頭ー柄山災害記念碑
3 所要時間 下り 1時間30分(往復4時間) 片道距離 約5キロ
(クリックして大きくして見てください)
分杭峠から大鹿村へは公共交通機関がないため、峠からは私有車を停めて15分くらい下り、遡って20分くらい上る方法を6回繰り返し北川露頭下の柄山の災害記念碑まで歩きました。距離は峠から5キロと短いのですが所要時間は見学を含め4時間もかかりました。鹿塩川の源流「三ツ沢」にはキクヤ茶屋跡があり、ここから先の秋葉古道は矢立木まで右岸側を通っていました。古びたテープや看板はところどころにありましたが、この先の道は左岸側を通っていました。左岸側は車道ができたため秋葉古道は廃道になり、街道歩きは国道152号をもっぱら歩きました。北川露頭の槙立には、石積みの整地跡、馬頭観音、北川三社神社、分教場頌徳碑などがあり営みを感じる跡がありました。この地は木地師が細々暮らす里でしたが、明治末から大正にかけては木材の伐り出しで大きな集落が出現したとのことです。大花沢橋のたもとには成田不動があり養蚕が盛んだった頃の面影が残っていました。大鹿村北川地区は三六災害で大被害があったことを災害記念碑で知りました。