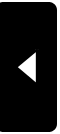2016年09月19日
北国街道(小諸宿~田中宿)
1 期 日 平成28年9月17日(土)
2 コース 小諸宿~滋野~田中宿
3 所要時間 約3時間 約10km
(クリックして大きくして見てください)
小諸宿から田中宿間は、中沢川、深沢川、大石沢川のV字河川が目につきます。江戸時代寛保2年(1,742)の戌の満水では、土石流によって両宿は壊滅的な被害を受けたましたが、復旧、復興にははかりしれない労力と費用と時間を要した思います。浅間山麓の傾斜が暴れ川となったことは容易に想像できましたが、各河川とも階段工によって砂防施設が施されていました。備えあれば憂いなし、災害の恐ろしさを痛感しました。
小諸城下町西はずれの分去れに、牛にひかれて善光寺詣りの言い伝えで知られる布引観音への道しるべ「ひだり布引山道」の道標が建っており郷愁を誘われました。東御市滋野駅そばの街道には、「雷電の碑」が建っていました。佐久間象山筆の碑(写真手前)は、破片を持ち帰ると立身出世する、勝負ごとに勝つ、との迷信が生まれ碑分が読めないほど破損し、明治中期に新しい碑が建てられたとのことです(写真後方)。
2016年09月14日
北国街道(小諸宿)
2 コース 小諸宿
3 所要時間 約2時間
(クリックして大きくして見てください)
小諸城は、城下町より下に城がある珍しい穴城です。大手門(四の門)と三の門(懐古園城門)の中間に小諸駅と線路がありますが、その施設は城門間を横切っており大胆さに驚かされました。宿場の荒町には、第二次上田合戦で和睦の調停を成立させたことで知られる海応院が、徳川家康の母の「お大の方」を弔うために作られた光岳寺等、由緒ある寺が点在しておりました。さらに、宿場の南の与良町に、民間に払い下げられた旧小諸城の銭蔵がありました。倉庫は意外に小さかったですが、小諸城を知る建造物として市の文化材に指定されています。また、往時の面影が色濃く残る、切り妻造りの本陣問屋や脇本陣、養蚕で隆盛を極めた商家の重厚な蔵造など、宿場にふさわしい町並みが形成されていて見応えがありました。
2016年08月27日
野麦街道(入山宿~水没記念碑)
2 コース 奈川渡ダム~入山宿~水没記念碑
3 所要時間 2時間 約5㎞
(クリックして大きくして見てください)
野麦街道の面影がのこる入山宿は、東京電力奈川渡ダムサイトの宮ノ下隧道の脇から入ります。(大白川林道から入るのが本筋)畑にいた古老に入山地区についてお話を聞きました。「かつては20世帯ほどあったが、今は10世帯になった」とのことです。急傾斜地で耕地が少なく寒冷地のため、減るのはしかたない成り行きだったと思います。江戸時代には幕府の要人が街道を頻繁に活用し、明治、大正時代にかけては、工女たちが往来しました。明治元年の建築を復元した旅籠・松田屋は、この地区一番の賑わいをみせていたそうです。今は周辺の廃屋も含めひっそりと佇んでいました。街道に宿場町はなく、工女、歩荷、牛方などが通る生活の道路でした。このため鉄道が敷設されると野麦街道は一気に衰退しました。山深い街道は誰一人会わず静まり返っていました。
2016年07月29日
東信州・中山道(塩名田宿~岩村田宿)
2 コース 塩名田宿~岩村田宿
3 所要時間 2時間30分 約6㎞
(クリックして大きくして見てください)
小諸への分岐、善光寺道標
佐久市岩村田は、平成の初めまで市街地を離れると、のどかな田園地帯が広がっていましたが、上信越自動車道、北陸新幹線の開通により縦横の道路が建設され大変貌を遂げています。
岩村田宿は江戸時代に中山道の宿駅が決まり発足しましたが、小諸へ通じる脇往還北国道(善光寺道)、甲州へ通じる佐久甲州街道、上州下仁田へ通じる下仁田道の分岐点として米穀の集積地として物資輸送上の要衝地でした。今は宿場の面影がほとんどなく、道標、道祖神のみがかつての面影を留める程度でした。本陣の代わりをつとめた西念寺は、屋根に内藤家、徳川家の家紋、仙石家の家紋「永楽通宝」が掲げられ威厳に満ちていました。由緒ある寺は品格を兼ね備えているものだと思いました。
2016年07月25日
伊那街道てくてく旅(信濃川島~宮木宿~伊那松島)
2 コース 信濃川島駅ー上島普門院観音堂ー徳本水
宮木宿ー春日街道交差点ー松島追分道標ー伊那松島
3 所要時間 約5時間 約14.5㎞
(クリックして大きくして見てください)
道標
JR信濃川島駅から程なく、辰野町上島区の普門院観音堂で重要文化財の「木造十一面観音立像」を見学しました。この仏像は仏師・善光寺住僧妙海作で緻密なカヤ材の一木造りの秀逸で、今を去ること650年ほど前の鎌倉時代末のものでした。片田舎の上島区の皆さんの保存活動に対し敬意を払い地域の宝物に合掌しました。辰野町今村の湧水「徳本水」は、岩間から湧き出る霊水で、炎天下の中でありがたい清涼水でした。宮木宿は残念ながら宿場の面影はほとんど残っていませんでした。伊那街道と春日街道(飯島町七久保から箕輪町大出)が交差する箕輪町大出交差点は、庚申塔が沢山残っていて民間信仰の一端を見る思いでした。箕輪町松島の追分は、松本と諏訪の分岐点で、趣のある立派な道標が残っておりました。
今回は、国道153号線を何回も横断する街道でしたが、前回と同様、中馬街道を強く印象づけられました。
善光寺街道協議会主催 参加者40名。
2016年07月17日
東信州・中山道(岩村田宿~小田井宿~追分宿)
2 コース 岩村田宿~小田井宿~御代田一里塚~追分宿
3 所要時間 4時間 約11キロ
(クリックして大きくして見てください)
一里塚
岩村田宿から追分宿は標高差が300メートルあり、ゆるい登りが続く街道でした。中間の小田井宿は、旅籠がわずか5軒ほどの小さな宿場で、大名の参勤交代は追分宿に宿をとり、小田井宿は姫君など女性が休泊したことから「姫の宿」と呼ばれました。本陣、問屋、旅籠は往時の姿を留めており静かな雰囲気の宿場でした。御代田の一里塚は、街道より7メートル離れた畑中に位置し遺存状態が良く、シダレザクラが植えられた珍しい一里塚でした。
2016年07月15日
東信州・中山道(追分宿~沓掛宿)
2 コース 追分宿~借宿間の宿~沓掛宿(中軽井沢)
3 所要時間 1時間45分 約5キロ
(クリックして大きくして見てください)
右北国街道、左中山道
追分宿は中山道と北国街道の分岐点に位置し、参勤交代の大名や善光寺参詣の旅人などで賑わっていました。現在は街道の雰囲気はありますが江戸時代の建造物は少なかったです。追分の分去れは、常夜灯、道標などの石造物が残っていて往時を偲ぶことができました。沓掛宿は地名が中軽井沢と代り、宿場を感じるものはありませんでした。両宿場は江戸時代に軽井沢宿を加え「浅間根腰の三宿」と呼ばれていましたが、現在と同様に隆盛していました。
馬頭観音の供養塔を道中で多く見かけましたが、これは軽井沢が標高1,000mの高冷地で寒冷地であったこと、さらに碓氷峠を控え物資運搬が困難を極めたためと思います。
2016年07月13日
東信州・中山道(望月宿~八幡宿~塩名田宿)
2 コース 望月宿~瓜生峠~八幡宿~塩名田宿
3 所要時間 2時間30分 約7キロ
(クリックして大きくして見てください)
瓜生坂標識 百沢「祝言道祖神」
「舟つなぎ石」
望月宿から鹿曲川を渡ると瓜生峠となります。「坂がきついから気を付けて」と古老から激励されましたが、木々のまにまに中山道の匂いがいっぱい感じられ気分よく歩くことができました。旧望月町の百沢には珍しい「祝言道祖神」がありました。男女が酒を酌み交わす華麗な祝言像で宮廷貴族風の衣装をまとっています。道祖神発生地の安曇野地方は、神々の装束像が通例であり類例のないめずらしい貴重な遺産です。八幡宿は千曲川の西岸に宿場が作られ、塩名田宿は東岸の川沿いに作られました。両宿は千曲川の氾濫による川止めで旅人の足が止められるため重要な役割を果たしていました。川越は想像以上に大変だったと思います。千曲川の中に面影を残す「舟つなぎ石」がありました。石の上部に穴を開けて船を繋いだ大岩で、「船橋」方式により渡川を確保し9隻を繋いだとのことです。
八幡宿では中山道を日本橋から歩いてきた4人組に会いました。素晴らしい男性仲間です。
2016年07月05日
北国街道(田中宿~海野宿~上田城)
2 コース 田中宿~海野宿~大屋~上田城
3 所要時間 4時間 約11㎞
(クリックして大きくして見てください)
海野氏の氏神
卯建(中央の家) (用水が流れる)
東御市の田中宿は、戌の満水の土石流が宿場を襲い壊滅的な被害を受けました。現在は田中宿本陣門、戌の満水供養塔、勝軍地蔵(善光寺地蔵と刻まれる)などに面影が残る程度です。偶然にも脇本陣をつとめたお店でお茶と昔話のご接待をいただきました。
隣接の海野宿は、田中宿に代わって本陣を勤めるようになりましたが、東信濃随一の豪族・海野氏の城下町で交通・商業の中心地でした。町並みは妻籠宿、奈良井宿につぐ当県3番目の重要伝統的建造物群保存地区に選定され「日本の道百選」に選ばれております。江戸時代の出梁造りの建物、明治以降の蚕室造りの建物が調和し、歴史の香りが残る県下随一の宿場建造物で美しさは際立っています。特徴は海野格子と卯建(うだつ)と出梁(だしはり)で卯建は防火壁の役割を果たし富裕の家の象徴で、逆説の「うだつがあがらぬ」という言葉が生まれました。
2016年07月02日
東信州・中山道(芦田宿~茂田井宿~望月宿)
2 コース 芦田宿ー茂田井宿ー大伴神社ー望月宿
3 所要時間 2時間30分(見学含む) 約6㎞
(クリックして大きくして見てください)
立科町の芦田宿から浅間山を東にみながら「間の宿」の茂田井を訪ねました。宿場は江戸時代の面影が色濃く残っていて、民家や造り酒屋、道路わきの水路から安らぎと癒しをいただきました。佐久市の望月宿は、かつて朝廷に名馬を収めた駒の産地で、本陣、脇本陣、旅籠が軒をならべていたとのことです。当時の面影は少なかったです。その中で真山家は当時の姿を伝えた出桁作り建造物として国の重要文化財に指定されています。
望月歴史民俗資料館で思わぬハプニングがありました。館内にいた先生が、尺八による「小諸節」をご披露してくださいました。家内と二人だけに演奏いただき恐縮しましたが、名人の尺八は炎天下道中に一服の清涼感でした。小諸節は江差追分節に通じる追分節の原型とか。
2016年06月28日
伊那街道てくてく旅(塩尻宿~小野宿~川島駅)
2 コース 塩尻宿ー上西条ー善知鳥峠ー小野宿ーJR川島駅
3 所要時間 約5時間(見学含む) 約12㎞ 同行者 43名
(クリックして大きくして見てください)
馬頭観音
小野家住宅(本棟造り)
伊那街道・三州街道は、塩尻宿から伊那、三河へ向かう中山道の脇往還として中馬の往来も多く交通の要路でした。塩尻宿から間もなく善知鳥峠となりますが、この峠(海抜889m)は、南は天竜川水系へ北は信濃川水系へ別れて流れる分水嶺で古来「水のわかれ」と呼ばれていました。小野宿は本陣、脇本陣は無く旧問屋「小野家」が役割をつとめていました。本棟造りで奥座敷は床が一段高くなった上段の間となっており見学をさせていただきました。街道筋には馬頭観音の石仏がたくさんあり中馬街道を彷彿させてくれました。
同行者(43名)の中に80歳の時に四国巡礼の旅を千曲市から往復歩いた人がいました。槍ヶ岳も登頂したとの事、怪物だと思いました。
2016年06月05日
東信州・中山道てくてく旅(長久保宿~芦田宿)
2 コース 長久保宿~笠取峠~津金寺~芦田宿
3 所要時間 3時間 約6㎞
(クリックして大きくして見てください)
土屋家 宿札
長久保宿から笠取峠間は、中山道の原道が残っていて新緑をかみしめながら気分よく歩くことができました。峠は江戸幕府の植樹政策によって植えられた樹齢300年の松並木があり素晴らしい景観を形成しています。しかし、松枯れの状況がひどく将来的には景観を維持するのは難しいのではないかと思いました。往時の旅人はここから浅間山を眺め気分を一新して江戸に向かったと思います。
芦田宿では本陣の土屋家住宅を見学させていただきました。奥の上段の間は京風づくりの貴重な座敷棟で往時をそのまま伝えていました。また、大名などの宿泊を今に伝える宿札が残されており昔を偲ぶことができました。
笠取峠について
・雁取峠といわれていたが、浅間山が良く見えるので笠をとった。峠に吹き荒れる風が強く笠が飛ぶなどから笠取峠とつけられたとのことです。
2016年05月24日
東信州・中山道てくてく旅(和田宿~長久保宿)
2 コース 和田宿~若宮八幡宮~三千僧接待碑~長久保宿~松尾神社
3 所要時間 5時間 約8㎞
(クリックして大きくして見てください)
濱田屋旅館
長久保宿は、中山道信濃26宿の中で塩尻宿に次ぐ旅籠数(最大43軒)を数え、北国街道へ向かう上田道と白樺湖を経由し茅野方面へ向かう大門道の分岐で、最大難所の和田峠、笠取峠を控え人馬の往来、物流の拠点として賑わっていました。現在は道路のルートは同じですが、田舎町であり横目に見ながら通過し賑わいを感じることはありません。宿場は本陣・問屋を中心に東西方面に「竪町」を形成し、南北方面に旅籠を中心とする「横町」を形成、交点に旧宿内で唯一旅館業を営む「濱田屋」が残っております。現在も大勢の旅人が利用しています。宿場は行政、地域が一体になって保存活動をしており十分楽しむことができます。
2016年05月11日
東信州・中山道てくてく旅(和田峠男女倉口~和田宿)
2 コース 和田峠男女倉口ー唐沢一里塚ー鍛治足一里塚ー和田宿
3 所要時間 約3時間 約6㎞
(クリックして大きくして見てください)
男女倉口
中山道最大難所の和田峠(標高1600m)男女倉は、旧石器時代から和田峠周辺の黒曜石集積地として全国に名だたる流通の拠点でした。奇しくも当日は、日本地質学会から「県の石」として初認定され、記念日に訪れることができました。男女倉口を下って間もなく唐沢の一里塚となります、一対で現存する珍しい一里塚です。
和田宿は本陣も旅籠も江戸時代の出桁造りや格子戸のついた姿を留めており、懐かしい癒しのひと時を過ごすことができました。宿場は隣の下諏訪宿まで5里18町(約22キロ)と長丁場のため、逗留する諸大名の行列や旅人が多く信濃26宿のなかでは規模の大きい宿場町でした。皇女和宮の御下向の際に宿泊されています。
2016年05月11日
北国街道てくてく旅(上田城~上田宿~岩鼻)
2 コース 上田城ー上田宿ー岩鼻
3 所要時間 2時間30分 約6㎞
(クリックして大きくして見てください)
東虎口櫓門 「真田石」
宿場の柳町 上田城の石垣
上田城はNHK大河ドラマ「真田丸」の舞台になり、県内外から大勢の観光客が来場していました。戦国の知将、真田昌幸によって築かれた平城で、400有余年の歴史をもちます。東虎口(出入口)櫓門は平成になって復元されましたが、現在は櫓3基と櫓門1基があります。かつて城の南は千曲川が流れる要害地で石垣や土塁が至る所に残っていました。櫓門の大石「真田石」は直径が3mあり、市街地北方にある太郎山産とのことです。場内の石垣の大部分はこの産地とのことで、築城には相当な労力と苦労があったと思います。もう一つ驚いたのは藩主居館表門が上田高校だったことです。教育に対する上田人の並々ならぬ思い入れと豪胆さを感じました。
上田城の外堀、矢出沢川が直角に曲がる地に、明治になって上田城を買い取ったこの地方指折りの富豪・丸山家が、城から運んで積み直した石垣が残っていました。見事な姿を留めており財力の凄さに驚きました。
2016年05月05日
北国街道てくてく旅(坂木宿~矢代宿)
2 コース 坂木宿ー横吹八丁ー上戸倉宿ー下戸倉宿ー矢代宿
3 所要時間 4時間 約12㎞
(クリックして大きくして見てください)
横吹八丁 名主・坂田家
下の酒屋 荒砥城址
坂木宿は戦国時代、信濃の勇将・村上義清の山城「葛尾城」があった地区で、町名は明治以降に坂城町となりました。街道には大壁造りの本陣表門が残っており、隣地に江戸時代に名主を務めた坂田家が姿を留めていました。北国街道の最大難所の横吹八丁は、高崖の山と千曲川に挟まれた天然の要害地で、通らなければ前後の坂木宿、戸倉宿に行けない危険な道で旅人の苦労は計り知れなかったです。
戸倉宿は上、下に分村したため、2宿が合宿した宿場でした。上戸倉宿は本陣門や老松は残っていましたが、下戸倉宿は18号沿いのため本陣の面影はなく、築250年の風格漂う下の酒屋が往時を留めていました。現在は千曲川の左岸に戸倉上山田温泉があり賑わっています。上山田の「荒砥城址」は村上氏の一族である山田氏が築いた城で、連郭式山城が再現され千曲川、戸倉上山田温泉、坂城町などが見下ろせました。
2016年05月05日
北国街道てくてく旅(矢代宿~松代宿~松代城址)
2 コース 松代城址、真田邸、文武学校、象山記念館、長国寺
松代象山地下壕
3 所要時間 3時間 約8㎞
1 期日 平成28年4月29日(金)
2 コース 矢代宿ー妻女山(登山)-松代宿
3 所要時間 4時間 約12㎞
(クリックして大きくして見てください)
旅籠「藤屋」 千曲川
松代城址、松代宿
松代城は武田信玄によって海津城として築かれ、待城、松城を経て真田時代に松代となりました。宿場は落ち着いた雰囲気があり、大河ドラマの影響もあって城下は活気に満ちておりました。特に印象に残ったのは、真田家の菩提寺、長国寺本堂屋根のいぶし銀の六文銭と、初代・真田信之公の霊廟屋でした。
矢代宿、妻女山(登山)
矢代宿は北国街道の迂回路・松代道(北国東脇往還)の分岐点として交通の要衝でした。宿名は矢代宿で、地域名は屋代です。加賀藩の定宿として伝馬宿として隆盛をみせていましたが、今は旅籠「藤屋」の看板と手すりに面影を見る程度で、宿場の面影はありませんでした
妻女山は川中島の合戦で有名な山で、山腹から善光寺平と千曲川の前景を見ることができました。
2015年10月11日
木曽・中山道てくてく旅(三留野宿)
2 コース 馬籠宿ー南木曽ー三留野宿ー十二兼ー野尻宿
3 所要時間 4時間30分 約14㎞
(クリックして大きくして見てください)
三留野宿は大火があったため宿場全体の面影はありません。屋号を残す建造物は残っており宿場を偲ぶことはできました。本陣は残っておりませんが、庭木だった枝垂れ梅の古木は残っており梅花時に思いをしました。三留野宿のメインは、三体の円空仏を所蔵する「等覚寺」。円空は美濃国に生まれた江戸時代初期の僧侶で12万体の仏像をつくることを祈願しました。信州の片田舎の南木曽町で円空仏と出会う喜びは格別で、木曽・中山道の最大のハイライトになりました。
三留野宿の南木曽町梨子沢は、昨年豪雨災害が発生しました。復旧状況をみましたが、木曽路は谷間の町であることを再認識し、防災対策、減災対策の重要性を感じました。
2015年10月09日
木曽・中山道てくてく旅(馬籠宿~妻籠宿)
2 コース 馬籠宿ー馬籠峠ー妻籠宿
3 所要時間 3時間30分 約9㎞
(クリックして大きくして見てください)
馬籠宿は坂道の宿場、島崎藤村・生誕の地、日本百名山・恵那山を仰ぐまちです。木曽11宿の中では唯一坂道の宿場ですが、外国人も大勢訪れる国際色豊かな観光地です。急峻な坂道は石畳で整備され、軒を連ねる宿場は江戸時代の面影を映す素晴らしい景観でした。そのうえ、文豪・島崎藤村を生んだ生家が本陣であり一層の箔をつけています。また、ここから眺める恵那山は地域のよりどころとして存在感があります。妻籠宿までの街道は、木々に覆われた山道で懐かしい匂いのするやさしい道でした。一石栃立場茶屋の茶屋番さんから木曽節のご披露がありましたが、声が透き通っていて良い思いでになりました。馬籠峠には正岡子規の「白雲や青葉若葉の三十里」の句碑もあります。
妻籠宿は山を背にした宿場で馬籠宿より一段と落ち着いた雰囲気でした。ここは飯田街道との合流点で交通の要衝として賑わっていましたが、敵の進入を防ぐ枡形や高札場も往時の面影を醸し出しており、今も残る江戸のたたずまいは馬籠宿と同様に美しかったです。間宿の大妻籠も卯建ちのある旅籠が昔ながらに残っており良い風情の家並みでした。