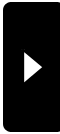2021年10月14日
保福寺道・東山道てくてく旅(浦野宿~小泉大日堂~上田原古戦場)
2 所要時間 車利用 浦野宿~小泉大日堂
徒 歩 小泉東信号機~小泉六地蔵憧~小泉高札場
~上田原古戦場、石久摩神社
・所要時間 約1時間30分 約3㎞
車利用 石久摩神社~中之条~千曲川渡河~上田宿
(クリックして大きくして見てください)
上田市小泉の保福寺道をはずれた山側に上田市有形文化財の小泉大日堂があります。参拝のため浦野宿から車を走らせて見学しましたが、飛鳥時代後期の創建で県下一の宝形造り堂とのことで見事な仏堂でした。(大日堂は五間堂、宝形造の大伽藍 で県内に残る中世の大規模仏堂の遺構として唯一)
小泉東信号機を北へ歩いて行くと見かけたことのない六地蔵憧がありました。(六地蔵憧とは道の辻などに建てられた供養塔で道行く人々の安全を祈願)さらに北へ進むと小泉の保福寺道沿いに高札場(復元)があり街道の面影を感じることができました。国道143号線を横断するまでは、ところどころに道祖神、庚申塔、馬頭観音などの石造物はありますが、見逃すこともあり不安な旧道歩きでした。国道を横断するとまもなく、天文17年(1548)に武田晴信と葛尾城主・ 村上義清が相まみれた上田原古戦場と石久摩神社があります。北国街道の合流はこの先3キロ、市街地のため車で千曲川を渡り上田宿へ向かいました。千曲川の渡河は水量に応じて架橋・舟橋・渡し船・徒歩などだったとのことですが、大河であり昔は大変だっただろうなと思いました。
2021年09月21日
保福寺道・東山道てくてく旅(青木村,国宝大法寺入口~上田市,浦野宿)
(クリックして大きくして見てください)
2021年09月12日
保福寺道・東山道てくてく旅(青木村、入奈良本・市之沢宿~国宝大法寺)
~青木村役場~昼付馬頭観音~浦野駅(うまや)推定跡
~国宝大法寺
2 車 入奈良本・市之沢宿~恋渡神社~奈良本・上手町宿
3 所要時間 約3時間 約7㎞(奈良本・上手町宿~青木村役場
(クリックして大きくして見てください)
保福寺峠から青木村最初の集落、入奈良本・市之沢集落(幕末には継荷客で栄えた宿)から恋渡神社、権現堂の涌井、上野坂は車を利用し、そこから先の大法寺までを歩きました。由緒ある瀧仙寺の麓の集落、上手町、川原町は古道の宿や市が開かれた町で面影があり、大門橋たもとの馬頭観音、道祖神には歴史を感じました。塩原牧寄遺跡(古代の牧場もしくは東山道に関連した遺構と推定)、太子堂公園下の東山道を踏みしめながら青木村中心部へと下り、国道を横切って役場の東を当郷(国宝、大法寺の地)へ向かいますが、途中には県下有数の大きさを誇る昼付の馬頭観音があり、浦野駅(うまや)跡と推定されるところを通過して、塩田平を見下ろす国宝大法寺三重塔を見学しました。平地を見下ろす台地に塔を建てることは、中世の山地寺院では典型的なやり方で、建築の美しさも配置の妙によって倍加され「見返りの塔」という名で親しまれているとのことです。飛鳥時代の大宝年間(701~)に創建された古刹ですが、信濃塩田平の奥座敷にこれだけの塔が存在することに不思議さを覚えました。街道の東山道は所々に標柱や説明看板があり歩きやすかったです。
2020年11月08日
保福寺道・東山道てくてく旅(保福寺峠~入奈良本宿)
2 コース 保福寺峠~青木村側一遍水(通行止め中断)
一遍水~清水茶屋跡~石川の陣場~入奈良本宿(往復車)
*峠から青木村側は道路崩落により一部通行止め
(クリックして大きくして見てください)
保寺峠山頂には、日本アルプスを世界に紹介した「ウエストン日本アルプス絶賛地」の碑と、県内では大きい馬頭観音がありました。馬頭観音は保福寺道が人馬の往来で賑わった証で、供養と安全を願う心が嬉しかった。
保福寺峠を境にする旧四賀村と青木村間は、県道181号線で結ばれています。11月下旬には冬期閉鎖されますが、その前に状況確認を含め青木村側を少し下って歩いてみましたが、人が歩いた形跡はありませんでした。翌日、予備調査を兼ね青木村中心部から峠へ車を走らせました。青木村「一遍水」上部は道路が崩落し工事中のため通行止めになっていました。「やっぱりそうだったか」と思いましたが、幸い歴史の道・東山道は、標柱設置がされており,一遍水から下りは古道確認ができました。青木村最初の宿場・入奈良本宿を経て恋渡神社をあとにしました。
青木村内の保福寺道は東山道に沿っており、青木村の皆さんの努力によって「東山道の歴史の道ウォーキングマップ」が作成されています。この道を上田へ向かえば良いことが判り、これからの街道巡りが楽しめそう。
2020年11月05日
保福寺道てくてく旅(松本市岡田宿~保福寺宿~保福寺峠)
2 コース 松本市岡田宿番所~松本市稲倉峠口道標
*稲倉峠は中断
四賀殿入り~保福寺宿~保福寺町勝立
*保福寺町勝立~一遍水までは県道を車
一遍水~保福寺峠
3 所要時間 約2時間(往復4時間) 約5㎞(往復10km)
(クリックして大きくして見てください)
(左江戸道、右みさやま」 *江戸道とは保福寺道
保福寺町番所跡
一遍水からの保福寺道
保福寺峠で足を止め絶賛
松本市岡田宿には善光寺街道と保福寺道が分岐する所に番所があります。この番所を右に稲倉方面に進むと稲倉峠の入口に「左江戸道、右みさやま」(江戸道とは保福寺道)と書かれた道標があります。ここを峠へ登りますが、しばらく行くと獣避けの防護柵が張り巡らされていました。通行に不安を感じ峠越えは中断し、戻って旧四賀村の殿入りまで車を走らせました。峠は昭和30年代までは、旧四賀村錦部の生活道路として利用されたと案内看板に書いてありました。殿入りから先に進むとまもなく保福寺宿になります。宿場は明治に2回の大火があり面影は少ないですが、本陣様式を忠実に残した三階建ての本陣問屋の小沢家と脇本陣・庄屋の両角家が宿場中央にあります。桝形を抜けると右側には番所跡、川を挟んだ反対側には曹洞宗・保福寺があります。保福寺町最奥部の勝立から先は道が途絶えており、県道181号線を車で一遍水まで行き駐車。一遍水から峠までは約1キロありますが、所々に案内看板や鉄パイプ柵があり迷うことはありませんが、人が訪れた形跡はなく寂しい道中でした。
2020年09月27日
谷街道てくてく旅(小布施宿~中野宿)
2 コース 小布施宿~東江部~西条~中野宿
3 所要時間 約3時間 (約9㎞)
(クリックして大きくして見てください)
道標の文字は「小布施に至る 〇〇に至る(判読不可)」
庚申塔に刻まれた「右中野 左飯山」(寛政12年)
小布施を後に中野宿へ向かいました。中野市との境界の殿橋信号機交差点の北に「小布施に至る 〇〇に至る(判読不可)」の道標がありました。ようやく谷街道の面影に会え嬉しかったですが、中野市東江部丁字路信号機のたもとには、庚申塔に刻まれた「右中野 左飯山」を見つけました。江部の入り口に道標があることは本により判っていましたが、どこにあるのかどのような型なのかは知りませんでした。まさか庚申塔の左右に小さく刻まれた道標だとは知らず随分さがしましたが見ることができ喜びは格別でした。西條地区はここを右折しますが、西條神社横の数基の馬頭観音には往時の面影が残っており馬への慈愛を感じました。中野市は近世においては幕府領中野陣屋がおかれ維新当時には中野県庁が置かれました。いまでは中野陣屋の名残があるのは跡地の石垣程度です。中野は山ノ内町志賀高原の渋峠を越える草津道で上州と通じ、立ヶ花の渡しで北国街道と通じる物資輸送の中心地であり、九斎市が立てられて賑わっていました。
2020年09月24日
谷街道てくてく旅(須坂宿~小布施宿)
2 コース 須坂宿~松川~小布施宿
3 所要時間 約2時間 (約6㎞)
(クリックして大きくして見てください)
「右 をぶせ道 左 大島道」
逢瀬神社北の分去れ「須坂道 山田道」の道標
(飯綱山、黒姫山、妙高山)
「蔵の街須坂」を後に中町を左折し春木町を下って小布施町をめざしました。春木町信号機の交差点には「右をぶせ 左大島」の道標があり、この先の松川(須坂市と小布施町の境)までは緩やかな坂が続きます。谷街道の面影は、春木町の道標と旭ヶ丘信号機交差点の馬頭観音くらいでしたが、松川周辺からの北信五岳・飯綱山、黒姫山、妙高山は、古今変わらぬ姿を見せており旅人に安らぎを与えてきたのだと、つい手を合わせてしまいました。松川橋は「信州の街道」本によれば、明治中ごろまで人馬が通るだけの木橋でしたが、橋には「谷街道」の文字がはっきりと刻まれています。逢瀬神社の北の分去れに「須坂道 山田道」の道標がありました。小布施の中心地の北斎館、高井鴻山記念館は平日にもかかわらず大勢の来訪者がおり賑わっていましたが、いい雰囲気だなあと感じたのは、栗の小径、陣屋小路の趣でした。谷街道は名前に似あわず台上の良い地形を通っている街道です。
2020年09月22日
谷街道てくてく旅(長野市綿内~須坂宿)
2 コース 長野市綿内~井上~須坂宿
3 所要時間 約2時間(約6㎞)
(クリックして大きくして見てください)
谷街道は稲荷山を起点に、矢代宿、松代宿、川田宿を経て綿内(長野市綿内)追分から須坂宿、小布施宿、中野宿、飯山宿へと続く街道です。街道は古いが、呼称は新しく明治20年が初出とのことです。命名は長野県庁で街道名の由来は、千曲川の下流「市川谷」に通じることから命名されたとのことです。それまでは上高井地方では「松代道」、下高井地方では「北国脇往還」と呼ばれていました。
矢代から綿内までは北国街道東脇往還(松代道)旅で実施しているため、今回は綿内追分(旧河東線綿内駅そば)を出発点に須坂宿までを歩きました。街道はほとんどが国道のため面影は薄かったですが、鮎川橋を渡った北側に故西蓮寺の墓地があり、地蔵尊の由緒書きに谷街道の表玄関として賑わったと記載されていました。北に進むと「墨坂神社」があり境内の欅は見事な古木で鬱蒼とした社叢をなしていました。かつては北信一帯の大祭として賑わいをみせていたとのことです。須坂宿は蔵の町並みが見事で江戸時代、須坂藩主堀氏の館町として繁栄し、明治から昭和初期にかけて製糸業によって隆盛を極め、大壁造りの町屋などの町並みは美しかったです。
2020年06月21日
戸隠道(表参道)てくてく旅(宝光社~中社~奥社)
2 コース 宝光社~火之御子社~中社~奥社(往復)
3 所要時間 約3時間(約7㎞)
(クリックして大きくして見てください)
270段の宝光社の石段を登り、社殿東側・神道(かんみち)を通って火之御子社、中社へ向かいました。中社は距離は短いのですが、神道に杉木立もあり古の雰囲気を漂わせています。戸隠信仰の中心地、中社の参道は、竹細工、戸隠蕎麦、宿坊が建ち並び大勢の人々が訪れていました。
奥社参道は一直線に続き、途中からの1キロ区間は、杉の大樹が連続しています。パワースポットとして人気があり、静寂の中に身を置くと霊験あらたかな風が頬を伝ってきます。背後に修験僧が修行したお山をいただいているためでしょうか、深山の地は不思議に気持ちが落ち着きます。急坂を登ると正面に奥社本殿が見え、天照大御神が天の岩戸にお隠れになった時、無双の神力で岩戸を開いた天手力雄命が祀られています。一段下がったところに、水を司る九頭龍大神が祀られています。
2020年06月08日
戸隠道(表参道)てくてく旅(善光寺~大座法師池)
2 コース 善光寺~湯福神社~七曲り(カット)~荒安~
皇足穂命神社~大座法師池
3 所要時間 約3時間(約9㎞)
(クリックして大きくして見てください)
善光寺を起点にする戸隠表参道は、善光寺西の湯福神社から左へ一方通行車道を行きます。やがて雲上殿―往生寺に通じる道路と交わり七曲りへ。七曲りはかつて戸隠道表参道最大の難所で急な登りがつづきましたが、現在は片側一車線の舗装道路になっています。道路は6月まで一部区間がスノーシェイド工事のため片側通行になっていました。七曲りは狭くて急で車の往来が激しいため危険を回避し車で通過しました。スノーシェイド上部から再び歩きリンゴ園を登り切ったところが荒安です。交差点に「左とがくし」と刻まれた道標があり、さらに進むと飯綱社の里宮「皇足穂命神社(すめたるほのみこと)」があります。この先の古道はバードラインに並行した舗装道路ですが、行き交う車、人は皆無で、大座法師池までは緩やかに登っていきます。遠方に飯綱山を仰ぎ、新居住地が散見されると間もなく大座法師池に到着です。
2020年06月04日
戸隠道(表参道)てくてく旅(大座法師池~宝光社)
2 コース 大座法師池~大谷地湿原~一之鳥居~大久保茶屋
~祓沢道標~宝光院
3 所要時間 3時間(約10㎞)
(クリックして大きくして見てください)
大座法師池から宝光社までの約10キロ区間は、道標が適度に設置され、ルートがしっかりしていて落ち葉が堆積し、新緑、満開のレンゲツツジ、小鳥のさえずりがあり気分良く歩くことができました。
大座法師池に隣接する駐車場に車を停め出発しました。大谷地湿原の脇道を進み戸隠古道の標識に沿って約3キロ進むと戸隠神社一之鳥居に出ます。かつての石造鳥居の残骸、再建された木造鳥居の撤去の歴史について立て札によって名残を知ることができます。一之鳥居跡近くの道標には、「従是中院神前迄53丁」の文字が刻まれています。ここを起点に一丁ごとに町石(1丁は109m)があったと言われていますが、現在はそのほとんどは新しい町石です。一之鳥居より7丁目に大久保の茶屋があり、現在は2軒が営業をしています。ここは古間、牟礼方面からの「戸隠下道」が合する交通の要地にあたり、戸隠・上野・鬼無里方面との中継所として馬小屋も数棟置くほどの賑わいだったとのことです。しばらく行くと、中社と宝光社の分岐点を示す祓沢の道標があります。右 ちゆうゐん(中院)、左 ほうく八うゐん(宝光院)と読む梵字です。宝光社は石段が270段あり樹齢600年といわれる杉木立に囲まれています。
2019年11月02日
秋葉街道てくてく旅信州編(梁木島番所~下市場諏訪社)
2 コース 飯田市南信濃
八重河内・梁木島番所~梶谷橋~梅平~和田・下市場諏訪社
3 所要時間 約1時間30分 約4㎞
(クリックして大きくして見てください)
飯田市南信濃八重河内には梁木島番所があります。この番所は当所、青崩峠下にありましたが、天明7年(1787)3月、青崩峠が崩れたことにより現在地に移転しました。梁木島番所の特徴は、遠山領内から出る榑木について、和田役所から出した書付無き者は一切通さないよう番人に厳しく申しつけた点です。これは山間の番所の役目を良く現していますが、近郷の者は手形を必要とせず、秋葉山への道の者や商人も所在がはっきりしていれば通したとのことです。現存の建物は多少手が加えられていますが、面影を良く留めていました。番所から和田の宿場までは、約4キロありますが、八重河内、梅平の集落は残っており街道の雰囲気を味わうことができました。和田の下市場諏訪社は、遠山谷の多くが八幡社にもかかわらずここは諏訪社です。年末には八幡社と同様に霜月祭り行われています。
2019年10月12日
大笹街道てくてく旅信州編(須坂・黒門~菅平・供養塔)
2 コース 須坂市黒門~峰の原・菅平グリーンゴルフ場前~
菅平供養塔
3 距 離 約3.5㎞(大笹街道)
大谷林道車移動 約6㎞
(クリックして大きくして見てください)
人工的に造られたもの
往時を偲ぶ石仏
大笹街道の黒門から供養塔間は約3.5キロあります。クマ笹が茂る巾1メートル程の急峻な山道で、毎年春になると仁礼会の皆さんが草刈をし保存管理に力をそそいでいます。(令和元年は5月26日実施)
街道の情報については事前キャッチしましたが、未経験のため峰の原高原・菅平グリーゴルフ場の手前まで車で移動しました。その後、逆に須坂方面へ向かって「土手道」を確認しながら歩き往時の歴史遺産を体験しました。峰の原高原は標高が1,500mと高く積雪などにより旅人は道を見失うなど遭難し難渋を繰り返しました。
土手道は人工的に造られたものです。高さ1メートル程の盛土がされ人馬が歩きやすいように造られました。道には観音菩薩の石仏が随所にあり苦難の歴史を物語っていました。目的地の菅平供養塔は見つけることが出来ませんでした。次回訪問時の楽しみにしました。
2019年10月12日
大笹街道てくてく旅信州編(須坂市仁礼宿~黒門)
2 コース 仁礼宿~仁礼西原~石小屋洞穴~黒門
3 距 離 約6キロ
仁礼宿歩き 所要時間 約1時間 約1キロ
仁礼宿西原~石小屋洞穴~黒門 車移動
(クリックして大きくして見てください)
江戸時代、北信濃と上州を経て江戸を結ぶ本街道は、北国街道―中山道が正規ルートでした。大笹街道は須坂市福島を起点に上州を経て江戸へ行く街道です。距離が短いため経済的効果が大きく物資郵送のバイパスとして中馬稼業で賑わっていました。信州側唯一の宿場は仁礼宿です。県下有数の大きな馬頭観音碑がありますが、これは仁礼の皆さんが、最大難所の峰の原、菅平を無事に通過できるよう、馬への慈愛を込めて安全と感謝を表したものと思います。仁礼宿関谷には、通過する荷や旅人を監視した口留番所跡が、さらに進むと立派な長屋門の新問屋・駒津家などがあり往時の雰囲気をとどめていました。宿場のはずれの西原には、線刻の観音菩薩石仏もありました。宿場の保存活動は、地元の皆さんが熱心に行っており石柱案内もあり歴史を良く知ることが出来ました。
この先の黒門までは約5.5キロの道のりになります。単独行動だったこと、初めて体験する道だったこと、アスファルト舗装で急坂が続くことなどから危険を回避するため車で移動しました。黒門手前には、珍しい石小屋洞穴がありました。洞穴は縄文草創期以来各時期にわたり使用された狩猟のためのキャンプ地で、日本最古唯一の微隆起線文土器などの遺物も発見されたとのことです。黒門は大谷不動尊奥の院入り口にあたり、大笹街道最大難所の急峻な山道との分岐点です。黒門については名前の由来は不明ですが、由緒ありそう。
2019年09月02日
北国街道てくてく旅信州編(長野市・新町宿)
2 コース 善光寺~吉田神社~穂積、徳間、東条~田中信号機
田子~飯綱町牟礼平出追分
3所要時間 3時間30分 約9㎞
(くりっくして大きくして見てください)
「右飯山、中野、渋湯、草津道 左北國往還」
北国街道の追分道標
新町宿は現在の若槻地区に当たる稲積、徳間、東条の三村で一宿を成した宿場です。穂積村は上旬の10日間を、中の10日間を徳間村、下の10日間を東条村が伝馬役を担っていました。宿場は善光寺宿から4キロほどと近いため一般客の宿泊収入が限られており台所事情は苦しい宿場でした。
善光寺宿から通称相ノ木通りを東に進むとまもなく吉田神社になります。境内に全国68の一宮の石祠が並べられおり印象深かったです。浅川を渡ると間もなく新町宿となりますが、問屋は往時の面影がなく史跡看板で知る程度でした。しかし、町並みは昔日の風情が漂っていました。徳間橋を越えた北の三差路には、飯山街道と北国街道の分岐点を示す「右飯山 中野 渋湯 草津道。左北國往還」の道標がありました。田中の信号機を越えて田子に入ると旧酒造家の表門には、飯山城の裏門を移した門が建ち、横に明治天皇御小休所碑がありました。街道の家並みが終わるとリンゴ畑の急な登り坂が続き、やがて飯綱町牟礼平出に出ます。平出は北国街道東脇往還(長沼道・松代道)と北国街道が分岐する追分で、道標は民家の敷地内にありました。
2019年08月28日
北国街道てくてく旅信州編(信濃町・古間宿、柏原宿、野尻宿)
2 コース 飯綱町牟礼・小玉一里塚~信濃町・落影~小古間~古間宿
~柏原宿~貫ノ木~野尻一里塚~野尻宿
3 所要時間 約3時間30分 約9.5㎞
(クリックして大きくして見てください)
古間宿(信濃町)…柏原宿と二宿で一宿の役割
飯綱町牟礼の小玉坂から信濃町小古間は、中部北陸自然歩道に指定され、美しい日本の歩きたくなるみち五百選に認証されています。小玉坂峠の茶屋跡には小玉一里塚の標柱が立っていました。道は簡易舗装されており杉木立が連なっていて歩き易かったです。森の中を抜けると広々とした田畑が広がり、落影(信濃町古間)、小古間集落へと続きます。ここは北信五岳の眺望に恵まれた小盆地で素朴な村里の風景が昔日の郷愁を誘っていました。往時は夏の霧、冬の豪雪に見舞われる名うての難所として知られていたとのことです。当日は雲がかかっていて山頂は見えませんでした。古間宿は柏原宿と鳥居川を境に連続する合宿で、問屋業務を月の後半だけ分担していました。本陣がないため、諸大名などの宿泊はなく、商人に多く利用されていたということです。古間は古くから「信州鎌」の名で知られており、当日も一軒の鍛冶屋からトンチンと音が聞こえてきました。お土産に手づくり鎌1本を購入しました。
柏原宿(信濃町)…俳人一茶のふるさとの宿場
古間宿のはずれの鳥居川を渡ると柏原宿になります。古間宿との合宿で問屋業務を月の前半分担っていました。宿場は国道18号線に面しており面影は薄いですが、かつては加賀百万石前田候の参勤交代における本陣として潤っていました。東から飯山道、西から戸隠道が合流する所で物流の拠点としても賑わっていました。
俳人小林一茶の故郷としても知られ訪れる人が多いです。旧居の土蔵は塗り替えられていますが、往時の風情を色濃くとどめており国の史跡になっています。柏原宿は北国街道の新井(新潟県)と善光寺の中間点で、どちらからも徒歩で一日の旅程でした。
野尻宿(信濃町)…北国街道筋信州最北端の宿
国道18号線沿いの貫ノ木と野尻宿の中間に桜の木が植えられた一対の野尻一里塚があります。貫ノ木は関ノ城(カンのキ)で、室町時代に関所があったところです。野尻宿の南には「従是飯山・川東道」の分岐道標があり、野尻湖畔沿いに飯山・川東に通じる道があります。野尻宿は信越国境に位置し湖畔にある宿場で、往時は旅籠十数軒を数えていましたが、現在は立て札のみで宿場の面影はありません。
2019年08月02日
北国街道てくてく旅信州編(飯綱町牟礼宿)
2 期 日 令和元年7月31日(水)
3所要時間 2時間 約4㎞
(クリックして大きくして見てください)
牟礼宿は加賀藩の参勤交代における中間地点の休憩所として、佐渡の金銀荷を付け替えた場所として、本陣を中心に賑わっていました。
牟礼の「いいづな歴史ふれあい館」で宿場の町並みを再現したジオラマシアター、展示物な
どを見学して出かけました。印象に残ったのは、武蔵(江戸)と加賀(金沢)の中間点を示す道標「武州加州道中境碑」、牟礼宿ができる以前からあった古刹・徳満寺入口の堂々たる鐘楼門、死後の世界をつかさどる十人の王を祀った十王堂まえの落ち着いた雰囲気の十王坂、加賀藩の参勤交代では中山道碓氷峠に次ぐ難所であったという小玉坂などが往時の香りを留めており印象に残りました。
2019年07月26日
北国街道東脇往還(松代道)てくてく旅(長野市豊野神代宿~飯綱町牟礼)
2 コース 長野市豊野駅~神代宿~神代坂~白坂峠~三本松~牟礼駅
3 所要時間 3時間30分 約8㎞
(クリックし大きくして見てください)
北信濃鉄道豊野駅からほど近いところに多賀神社があります。神代宿(長野市豊野)はこの辺りから始まりますが、宿場沿いに「神代村道路原標 御番所跡」と刻まれた石柱があり宿場名の意味が理解できました。神代宿はかつて飯山街道と交差する交通要衝の地として栄えましたが、現在は宿場の面影は少ないです。飯山道道標「是は善光寺ミち」と刻まれた石柱文字と観音堂階段下の石仏群に往時の面影が残っていました。宿場は、北国街道東脇往還の宿として指定されましたが、飯山街道の宿駅の方が早く、そのことは番所、本陣、脇本陣ともに飯山街道沿いの横町にあったことから読み取ることができます。(JR飯山線の始発駅は豊野駅。神代は今昔ともに交通の要衝地)神代宿を出ると街道はリンゴ畑に覆われた山道となり長く厳しく続く神代坂が待っていました。旧道は草が繁茂し歩くのは無理のため新道を歩きましたが、白坂峠を越え、桃で有名な丹霞郷を進むと北国街道と合流し牟礼宿へと続きます。途中に三本松がありますが、ここは行人塚で修行者や行き倒れの旅人を葬った跡とも言われています。草むらの中に「父ありて明ぼの見たし青田原」の一茶句碑がありました。一茶が15歳で江戸へ奉公に行くとき、父が柏原宿から牟礼まで送って来て別れた場所とされていますが定かではありません。
2019年05月31日
仁科街道(千国街道)てくてく旅(松本市神林町神道標~松本市島内長尾道の渡し舟場跡)
2 コース 松本市神林町神道標~島立北栗道標~島内小柴~
島内高松南部公民館道祖神~島内長尾道の渡し舟場跡
3 所要時間 合計4時間(2日) 約10㎞
(クリックして大きくして見てください)
神林町神道標~島立北栗道標~島内小柴
(5・25 2時間30分 約6㎞)
神林町神道標から北の町神公民館そばに山の神と石造群の立て札があります。説明書きに「山の神は山を守り山を掌る神で農事の季節になると山を下り、里の神・田の神になる」と書かれ、御嶽大権現、二十三夜塔、馬頭観音などの石神仏像が祀られていました。森羅万象の祈りが伝わってくるような気がしました。その先の同町内には「旧上神林村高札場」がありました。松本市特別史跡になっていて「高札場は千国街道沿いにあり……云々」と書かれていました。さらに北の鎖川には、梶海渡橋、千国橋、仁科橋があり橋名に街道名が付けられていました。親近感と共に仁科街道をさらに実感しました。島立南栗公民館の道祖神には「道祖神は郷倉屋敷添いの南北に通じる仁科道に面し……云々」と書かれていました。さらに北の島立北栗交差点にも道標がありましたが、字は残念ながら削られておりその内容は不明です。
島内小柴~島内長尾道の渡し舟場跡
(5・26 1時間30分 約4㎞)
島内小柴から国道158号線を横断し日本浮世絵博物館、松本筑摩高校、高松寺へと続きます。島内高松南部公民館には道祖神、庚申塔などの石造物群が、島内高松本村公民館そばには道祖神、二十三夜塔などがありました。その先の長尾道には、かつて梓川を舟で渡った「長尾の渡し舟場跡」があります。松本の島内高松から安曇野の上真々部を結ぶ渡し場で糸魚川街道と合流しました。
2019年05月30日
仁科街道(千国街道)てくてく旅(塩尻市洗馬宿~松本市神林町神道標)
2 コース 仁科街道は洗馬宿から分かれて3ルートあります
①朝日村から山形・波田に抜ける山沿いルート
②奈良井川左岸を進む川沿いルート
③岩垂から今井を通る中央ルート
今回は②のルートを歩きました
塩尻市洗馬宿~琵琶橋~本洗馬~岩垂道標~
松本市笹賀今村道標~笹賀神戸~神林町神道標
3 所要時間 合計4時間(2日) 約10㎞
(クリックして大きくして見てください)
「左仁科道 右松本道」
洗馬宿常夜燈~琵琶橋~本洗馬~岩垂道標
(5・23 所要時間 2時間 約5㎞)
仁科街道は中山道と善光寺街道が分岐する洗馬宿から北西へ行きます。奈良井川に架かる琵琶橋を通過し本洗馬、岩垂へと続きますが、琵琶橋のたもとに馬頭観音等の石造物群が、本洗馬には由緒ある東漸寺の古木の桜、長興寺の美しい庭園、江戸時代の文人・菅井真澄が逗留した釜井庵などがあり集落とマッチし見所が多いです。岩垂地区はかつて一村をなし天領(幕府領)と私領(高遠領)に分けられていましたが、両方の名主から等距離の位置に塩尻市唯一現存の高札場があります。岩垂は農村地帯ですが豪壮な建物が多く威厳を感じました。集落のはずれに「左仁科道、右松本道」の道標と道祖神がありました。仁科街道を示す重要なもので面影を身近に感じることが出来ました。
馬頭観音他
「右今井道 左神戸道」
松本市笹賀今村道標~松本市神林町神道標
(5.24 所要時間 2時間 約5㎞)
松本市南部の奈良井川沿いの一番外れの集落が松本市笹賀今です。町会の公民館前の辻に「右松本道 左大町道」の道標がありました。道標の大町道は仁科街道を表すもので道祖神が彫られていました。この先の上小俣、下小俣には人馬の往来があった証の馬頭観音、道祖神が結構残っていました。さらに先の笹賀神戸には切妻屋根に「雀おどし」の棟飾りの付いた本棟造りの豪農屋形が数多くあり驚きました。史跡案内板によれば中世のころから「神戸の舘」はあったとのこと、歴史と風格が漂っていました。さらに北へ行くと神林町神の三差路に「右今井道 左神戸道」の道標がありました。道標は小さいですが笹賀神戸から洗馬へ通じる道しるべであり旅人にとっては大切なもので、見つけることができ嬉しかったです。